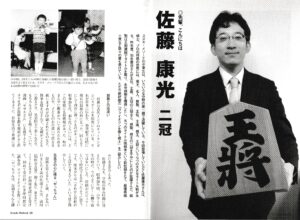第13回「子どもが社会のルールを学ぶ時」
-e1661659611607.png)
小児神経科医
植松有里佳
こんにちは。お久しぶりです。
以前Fruitfulの記事を初めて書かせていただいてから3年が経ちました。幼稚園の年中だった娘も小学校2年生になり、できるようになったことも多い反面、子育ての難しさも感じています。今回も発達支援の現場で感じることをふまえて、私のこれまでの子育ても振り返りながらお届けします。
本当にできないのか?
発達支援の診察室では、「授業に参加しない。」「クラスのルールを守れない。」というような相談を受けることがあります。集中力が続かないのかな? とか、やるべきことが難しくてわからないのかな? とかその原因になることを探すわけですが、どうもそれらしいことが見つからない場合もあります。
つまりそれほど集中力に問題があるわけでもなく、先生の指示が理解できないのでもない様子なのです。家庭では困ったことがなかったりもします。
本人に合わせ過ぎた結果
実は、「本人に過剰に合わせた子育ての結果」という場合が最近よく見受けられるように思います。
ご家庭ではいつも本人に合わせて、本人がしたいタイミングで本人がやりたいことをやってきた結果として、学校や集団の場では、自分がやりたくない事、面倒くさい事や興味が持てない事をしない、みんなのペースではやらない・・・ということが起きてしまいます。
親御さんもお子さんにうまく対応することに慣れてしまって、ご家庭でそれほど困ることがなかったりします。
親御さんの想い
親御さんの中には、自宅では勉強しているのなら、後は好きなことをして過ごしてくれれば良いと考えておられる方や、学校や勉強で疲れているから身支度や明日の準備などは親がやってあげることにしているという親御さんもいらっしゃいます。
この子には、うまくやれる力、成功する力があるのだから得意なことを伸ばして、成功できるように手伝いをしてあげるのだということもあるのかもしれません。

幼少期には手を貸して、できることを増やす
本人の年齢や力に合わせて、できるように促し、工夫して正しい方向に導き、一緒にできたことをほめて自信をつけ、繰り返して自らの力でできることを増やしていくことはとても大切です。
できないことに対して感情的に怒ったり、無理やり決められた枠に押し込んだり、その枠に入らないことに落胆することでは、良い結果に結びつかないでしょう。
ほめて育てることが基本ですが、ほめて育てることは叱ってはいけないということではありません。
冷静に物事の善悪や、やるべきことはやると教えることは幼少期に必要なことです。特に食事、着替えなどの生活力をつけることや身近な人との関係性や礼儀を教えることは、社会に出るために最も必要であり、親御さんの子育ての力に委ねられている部分が大きいと思います。
あなたのお子さんが、何を大切に生きていってほしいか、ぜひ考えてみてください。
子育ての結果
前述のように、本人ができる能力があるのに過剰に合わせすぎた結果、やりたくないものはお父さん、お母さんがやるからやらなくて良いと子どもは感覚的に間違った習得をしてしまうことがあります。このまま成長すれば、問題はますます大きくなって思春期に困ることになっていきます。
時間がないから全部やってあげたり、反対にいきなり全てを子どもにやらせるのではなく、まずは親が手本を見せて、一緒にやる、親が確認してあげて間違いも含めて教えていくなど丁寧な子育てというのは、お子さんの人生を必ず実り豊かなものにしてくれると思います。
社会のルールを学ぶ時
子ども達どうしの関係の中でも子どもは社会のルールを学んでいきますが、そんな中でも親御さんの姿勢は重要です。
友達とふざけて悪さをして、学校の備品を壊してしまった時など、先生から注意を受けて学ぶこともあるかもしれませんが、それ以上に子どもは、それを聞いた親御さんがすぐに学校に連絡し、先生に謝りに行く姿を見て、多くのことを学ぶことでしょう。
当然のことながら、親ができないことは子どももできません。
レッスンでのエピソード
私の娘が4-5歳くらいの頃のことです。娘は教室で先生とレッスンをすることが小さい頃から大好きです。
しかし、ある時レッスンで自分が思うように弾けないことで怒り出し、不貞腐れて先生がお声がけ下さっても返事もせず、言われたように弾かないどころか八つ当たりするような態度をとったことがありました。それは、疲れていたとか、あまりにも小さい頃にあった恥ずかしくてどうしても弾きたくないという様子ではありませんでした。
私は、先生に「大変失礼な態度で申し訳ありません。これ以上レッスンをお願いするわけにはいきません。今日はここまででお願いします。」とお話しし、教室を出ました。娘は大好きなレッスンが中止になるのは嫌なので大泣きしてさらに騒ぎましたが、そのまま連れて帰りました。先生は何とかレッスンが続けられるようにお声がけ下さっていました。私は決して冷静ではいられず、目が引きつって、さぞ怖い顔をしていたと思います。
家に帰って落ちついてから、人にものを教わる時の態度について娘に話をしたらまた大泣きしました。それがまた落ち着いてから今後もこうなったらすぐに帰りますと伝えました。娘の父である私の夫は、「気持ちよくレッスンを受けられないなら、もうこれからは通うことはできないよ。これはヴァイオリンの問題ではなくて、これからいろいろな人に教えてもらいながら生きていくために大事なことなのだから。」と話をしました。娘はぽろぽろ涙を流して聞いていました。
意味はしっかりわかっていなかったかもしれませんが、こうなったらレッスンができなくなること、やってはいけないことがあることは覚えたのではないかと思います。それ以降は、このような事態になることはありませんでした。
前述のような上手な方法とは程遠いわけですが、私としては子どもを何とかなだめてお稽古することよりも善悪を教えることが大事なことでした。そんな母娘をいつも温かく見守って下さる先生には、心から感謝しております。

失敗の保障
社会に出るまでに必要なことを習得するために、お子さんはたくさんの経験を積み、その過程でたくさんの失敗をすることでしょう。親御さんがお子さんの失敗を恐れずに、完璧を求めず、致命的な取り返しのつかない失敗以外はぜひお子さんに経験させてあげてください。
失敗しても次に挑戦していく子どもの姿はとても美しいです。
そしてそれを身近で見守れることが、子育ての喜びなのではないかと思います。
プロフィール
植松有里佳
7歳の女の子の母。小児科医。専門は小児神経学で、神経難病からてんかん、発達障害まで幅広く診療している。


今回は、実際の診療でのケースを例に、メディアとの接触時間が子どもの生活に与えてしまう影響の大きさを考えます。

前回に引き続き、現代の生活の中に深く入り込んでいる映像メディアに潜んだ諸問題を、目に見えるようにして解説していきます。今回は学齢期以降の子どもにフォーカスを当てます。

現代の子育てで最も気になるトピックスの一つであるメディアとの関わり方について、小児科医の目線からの提言です。

第4回の記事に寄せられた質問への回答から、思春期に向かう子どもたちにとって、あるいは親自身が何を指針とするべきかのヒントが示されています。

子どもたちが遊びを通して身につけていくものは何なのか? 家でも外でも、家族や仲間と自然に育むことのできる能力についてお話しします。

夏休みの時期につい乱れがちになる睡眠。年齢に応じて必要な睡眠時間や、学習との関連、さらにお昼寝をした場合の就寝時間への影響をお話しします。

今回は思春期の子どもの身体の発達と、それに伴う心理の変化(=二次反抗期)に対し、どう対応していくのが良いのか・・・小児科医の立場からの提言です。寄せられた質問への回答もございます。

子どもは運動機能の発達が進むと、言葉の発達も促されます。さらに年齢とともに自我が目覚め、一次反抗期へ・・・そのとき、周囲の大人の心構えはどうすれば良いのでしょうか?

生まれてから4‐5歳まで、子どもはどのような段階を経て運動能力を発達させていくのでしょうか?全身運動から手先を使う作業に至るまでの道筋を解説します。

子ども時代に大切なことを小児科医の視点からお届けするシリーズ。今回は親子関係の基盤や子どもの成長の土台となる「愛着形成」についてです。「愛着」って何?どうやって育むの?うまくいかないとどうなるの?など、様々な疑問を解説します。