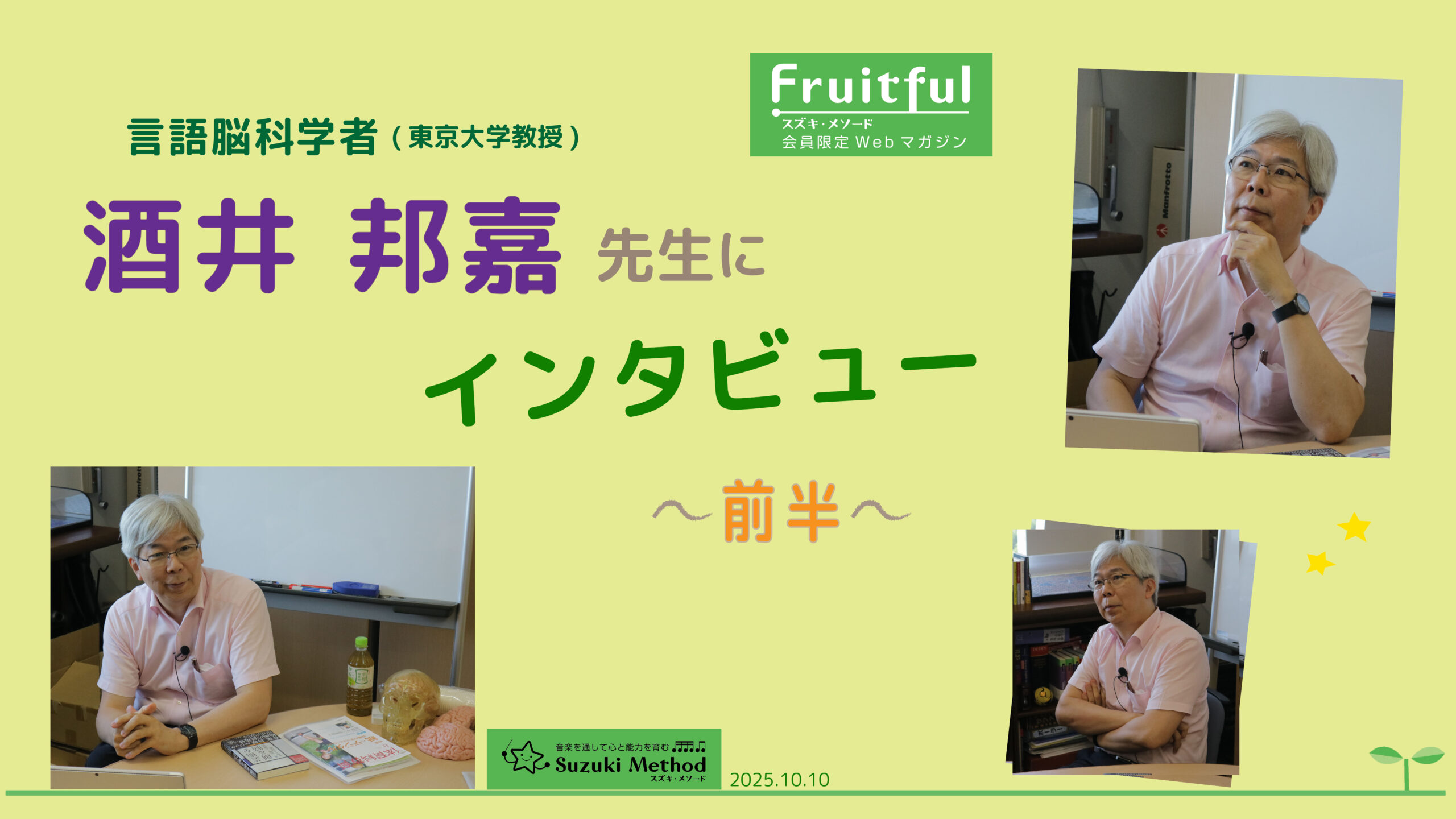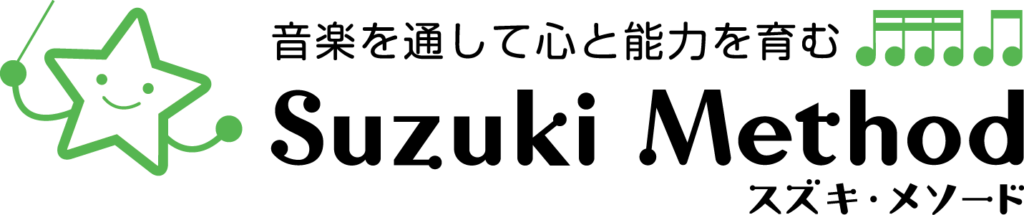
特別編 酒井邦嘉先生にインタビュー[前半]
東京大学教授(言語脳科学者)
酒井 邦嘉
今回の「脳と能力」は、まさに東京大学とスズキ・メソードとの共同研究を実際に行っている日に、著者である酒井邦嘉先生の研究室にお邪魔し、共同研究について、そして先生のパーソナリティについてお伺いしました。
——それでは酒井先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ーースズキ・メソードとの共同研究で、もう8年くらいになりますでしょうか、長くお世話になっております。本当にありがとうございます。
こちらこそお世話になっております。
ーー今日はこの共同研究についてと、酒井先生のプライベートな部分も交えて(笑)お伺いしていきたいと思います。
Q1:
スズキとの共同研究について、まだよくご存じない方々のために簡単に概要を説明していただけますでしょうか?
はい。
鈴木先生が「母語教育法」ということをおっしゃったんですね。つまり日本語を皆さんが勉強しなくても苦もなく喋れる。そこには「どの子も高く良く育つ理想的な教育法がある」と考えられて、それに音楽教育が向かっていけば、完璧な教育法になるんじゃないかということに気づかれた。そこら辺は、「愛に生きる」の冒頭に詳しく書かれてますね。
僕もあの本を読んで非常にびっくりして…鈴木先生はあの時エウレカの状態だったと思うのですが、つまり「大発見をした!」という感じで「どの子も日本語を喋ってるんだ!」と周りに言ったら、周りがキョトンとして、「それは当たり前じゃないですか、先生」という感じだったわけですよね。
私は鈴木先生と直接お話しするチャンスは無かったですけれど、もし出来たら、やっぱりそこの所はお話ししたかったですね。素晴らしい。
私の研究の根幹なのですが、赤ちゃんの脳は言葉の仕組みを備えた状態で産まれてくる、もしそうでなかったら生後3年から4年くらいで言葉を話し始めたり、なんのレッスンも受けていないのに日本語の文法とか、複雑な五段活用とか、そういうものを覚えていないはずなのに、その規則に従って、「走らない、走ります、走る時、走れば、走ろう」みたいな風に言えるというのは驚きしかないわけです。
そのことを一番端的に明らかにしてきたのがノーム・チョムスキーというアメリカの言語学者です。僕はチョムスキー先生に出会ってから脳科学の分野でそれを検証しようという研究をずっとしてきました。そういう意味では、音楽教育というと今まで自分がやってきた研究とはだいぶ違うんですけれど、将来そういう研究が一緒にできたら良いなと、ずっと思い続けてはいたんですね。
そこに2010年、機関誌Suzuki Methodから取材を受けまして、その時に共同研究できたら良いですねみたいな話で終わっていて、それからずっと頭の中でアイディアを飼っていたというか・・・そうしたところでフッと思いついて、スズキ・メソードに私の方からアプローチして、「共同研究できるでしょうか?」みたいな話をしたら、返す刀で早野龍五先生(現スズキ・メソード理事長)からメールが返ってきて、それがちょうど早野先生が会長(当時)になられた時だったのですね。早野先生は東大の物理の同僚だったのですけれども、私は全然会長になられたことは知らなかったのでびっくりして、そこから話を詰めて、共同研究するということになったのが2017年でした。
その前から結構、種まきはしていたんです。私の頭の中で、芸術を対象にした研究ができたら良いなと思ったのは、『芸術を作る脳』(東京大学出版会)という本を書いた頃、2013年ですね。だから時系列的にはちょうど今との中間に位置してますよね。2010年くらいにお話をいただいて、それまで言語に集中して研究をやってきたので、音楽も自分の研究の一部に出来たらいいなと思っていたところで、指揮者で作曲家の曽我大介さんという方と対談をした『芸術を作る脳』という本になって・・・だいぶ頭の中で色々なものが整理されてきて、「音楽も言葉だ」という確信がかなり得られたところで、2017年に共同研究がスタートという感じです。気が熟したということだったんでしょうね。
無から有が突然生まれるわけではないので、やっぱり地ならしとか色んなアイディアとか、出会いとか、そういうものが大切だなあと、今回非常に強く思います。ありがとうございます。
——その結果、2021年と2025年に第1弾と第2弾の調査についてそれぞれ論文が発表されて、今第3弾の研究が始まっているということですね。
はい、実験というか調査が始まっています。
Q2:
スズキ・メソードのことはどのようにお知りになり、この共同研究まで至ったのでしょうか?
——そもそも2010年のスズキ・メソードの機関誌からの取材というのは、どういう経緯で行われたのでしょうか?
機関誌上で「音楽サイエンス Vol.1」という、音楽と科学に関する連載が始まったところで、編集部からご連絡をいただいたのが最初ですね。多分ご興味を持たれて、取材をされたのではないかと…そこら辺は編集部の新さんに聞いてみてください。で、喜んでお受けしたので、それがご縁で今でも新さんに機関誌含めてお世話になっています。
——マンスリーの方にも詳しく、これまでの研究の経緯は載っていますね。先ほどお話しの出ました、チョムスキーにご興味を持たれたというのはいつぐらいなんですか?
1996年、当時私は、まだ先端的だった人間の脳をMRIを使って行う研究を日本で始めたんですけれど、やっぱりまだまだ技術的に足らない部分があって、その研究のメッカであるアメリカのボストンに行ったんですね。
ただ向こうには人が集まりすぎているし、非常に組織だってない、カオスのような状態だったので、アメリカには来てみたものの、ちゃんと自分で研究テーマを見つけなければいけないというところで結構悶々としていて、テーマが定まりませんでした。
MRIの基礎的な技術を開拓しようというふうにその後1年くらいやってたのですけれど、それもこの先どうするかな、と悩んでいたところで、私が医学部にいた時の恩師の宮下先生という方がボストンのチョムスキーの所と共同研究を組むというプロジェクトが、ちょうど始まろうとしていた時で・・・向こうは向こうで橋渡しをしてくれるような人を探していたんですね。
言語学と脳科学というと当時ほとんど一緒にやっている人はいなかったんです。自分のところに話が来た時にも、全く当時は言語学を私は知らなかったのですが、ただこれはちょうど良い機会だと。
というのはつまり、人間を対象としたサイエンスをやる上では、言葉は一番の究極の山の頂のようなところにあるテーマなので、その話をいただいた瞬間に頭の中で何かが結びついて、「あ、これは行ける!」というか、ライフワークになるなというお題をいただいた感じだったので、もう二つ返事で行かせていただきました。
だから本当に偶然ではあるんですけれども、頭の中で人間を対象にした脳研究をやりたい、人間の脳でやるからには高次脳をやりたい、でも言語は自分は何も知らないので、どうしようと、うまく結びついて無かった時に、向こうからテーマを頂いたので、これはもうゼロからやっていっても楽しそうだと。
元々いろんな分野を…物理から生物学とか脳科学とか進んできたということもあって、新しいことに挑戦するということに全然臆するということがなくて、むしろ逆に楽しいという方に向かう気質だったんですね。それが良かった。
あとで、色んな楽器をやっているみたいな話になると思うんですけど、今やっているの4つ楽器は、すべて全くゼロからの体験を大人になってからしているわけですよ。はじめての時は、期待感と恐怖感、両方入り混じっているんですね。全く音が出なかったらどうしよう、みたいなね。だけど結局、恐怖感よりも期待感の方が優るという感じです。
だから新しい分野に入って、1からMIT(マサチューセッツ工科大学)1年生の学生に混ざって講義を聞かせてもらいました。その時私はポスドクと言って一応ドクター取って博士研究員という客員研究員の立場で行っているんですけれど、そんな立場関係ないですよね。本当に大学1年生に混ざって、言語学の演習をやって・・・英語がネイティブじゃないのでみんなが軽々解けるような、英語の長い文が出てきて樹構造で書いていくようなお題がどうしてもわからなくて、というのを繰り返してました。だけどやっぱり学ぶということに年齢は関係ないですし、興味や好奇心があれば何とかなるという、この後に繋がっていくようなきっかけを得ました。
ーーありがとうございます。言語に関する研究で、たしか「雪を降る」のような、聞いた瞬間に「えっ?」って脳が反応するようなお題をいくつか出して脳の反応を見るようなことを最初の頃されていたようにお聞きしたのですが、そのあたりのことをお伺いできますか?
最初の頃に行っていた研究ですね。人間の脳って非常に正確な文法というものをこなせるんですね。実際に使ったのは「雪が積もる」に対して「雪を積もる」という例文です。「雪を触る」っていうのは良いんですけれども、「雪を積もる」っていうのはすごい気持ち悪い感じがしますね。
その違和感というのは単なる「て・に・を・は」の問題というよりは、「積もる」という動詞と「雪」という名詞には意味的に非常に近い関係があるのに、「雪を積もる」と言うとなんで会わないのかな、「雪を触る」は別に問題はない、「雪を」というつながり自体も別にまずいということはない、ということは二つの単語の間の関係性が大事で、その形が組めるか組めないか、それがチョムスキーの生成文法の一番大事な部分だったんですね。まず二つのものをちゃんとくっつけられるかということなんです。
我々は、何か言葉を覚えるときには単語を一所懸命に覚えるという風に思われがちですが、大事なのは少ない単語であってもその組み合わせを変えていくということに妙があって、それがしかも子どもの時にできる、というのが実は一番大切な点だった。だから、それをテストするには一番単純で短い文であると良いので、そういう分かり易い例を使ってみたというわけです。
そうすると、実は文法的に正しいか間違っているかに反応しているんではなくて、文法的に判断している脳の場所が特定できて、それを文法中枢と呼ぶようになって、それが共同研究の中でも音楽の一番高次のエラーと全く同じ反応を示すということまで結びついてくるのですが、そういう意味では当時全くわからなかったことが解明されていくという研究の面白さですよね。言葉の、ある種間違いを正していって正確な形を作っていく樹構造(枝別れのような構造)というものを作っていくんですけれども、音楽も全く同じだと。その話は2010年のインタビューでも同じ話をしていて、それが今実ったという感じですね。面白いものですね。
——本当に興味深い話ですね。先生が以前出された本に、「脳の地図」という概念が紹介されていて、脳のこのあたりでは何を判断している、例えば単語とか文法とか意味とか抑揚とか、それぞれに対してそれぞれ反応する箇所が別にある、そういう脳内の地図みたいなものを特定されていらっしゃいますが、それが今の共同研究においては、音楽を聴く行為においてはどうなっているのかということの基になっているという風に考えて良いんですね。
音楽は音楽で言葉と少し違ったところがあって、例えばピッチやテンポやストレスの違いというものはある。そうするとそこは言語と似てるところはすごく多いんですけれども、必ずしも同じではなく、違うところもあるかもしれない。研究では演奏上の間違いに対する反応を見ながら、正しいと判断していても脳の使っている場所が違うはずだと考えていたら、実際違っていたわけですね。

——今どこの箇所を使っているかを特定するには、脳の血流が多くなった場所を検知していくんですね。
脳の使っている特定の場所の血流が上がることを利用しているので、音楽の判断でも、「ちょっと今テンポが速くなったかな?」という時とか「音がちょっとずれたかな?」とか「強弱間違ったかな?」みたいな、そういうところでは「あれ?」という、さっきの「雪を積もる」と聞いた時と似たような判断が瞬時に起きるわけです。
その場所は、実はちゃんと別れていて、で「雪を積もる」的な判断をしてることを音楽で実現した「アーティキュレーション」という条件があるんですけれど、その時は文法中枢をやはり同じように使っています。それは予想通りだったといえばそうなのですけれども、予想を立てるのに結構時間が何年もかかりましたし、それが実験で実証できるかどうかは、やってみなければわからないので、スズキの生徒さんにもたくさん協力していただいて、指導者の方にも生徒さんにも快く来ていただいて・・・そのおかげで、実現して、証明できて論文まで書けるというのは、ちょうどこう山登りの紆余曲折あって途中で五合目くらいで休憩して、また元気取り戻して頂上アタックみたいな感じで頂上に登れたというような感じでしょうか。
頂上まで登るとまた次の頂上が見えてくるので、さらにまた違った山に登りたくなるのが人情ですよね。それが第2研究という感じです。
Q3:
ここからは、先生のパーソナリティに迫る質問です。小さなころ、先生ご自身はどんなお子さんでしたか?
——ありがとうございます。ではここで一旦先生のパーソナリティに迫る質問ということでお伺いしたいと思います。
先生ご自身はどんなお子さんでしたか?
好奇心が非常に強かったのと、一人っ子だったという家庭環境が影響しているのかもしれませんけど、自分で考えて、自分で出来るまで考えるというか、あんまり親に相談できるという訳でもないので。兄弟がいれば気楽に聞けることも、親だとなかなか聞きにくい。だから自然と自分で考えるようになったので、それはこういう学者とか研究者にはある意味必要というか、向いている気質だったかもしれません。
で、先ほどちょっとお話ししたように好奇心が旺盛だったので・・・飽きっぽいところは裏面としてはあるんですけれど・・・ただやり出すとすごいのめり込むタチだったので、だから例えばヴァイオリンを始めたらやっぱりそれなりにやりたくなって、当時はスズキの教本使ってたんですけれど、課題の先の方まで自分でやってからレッスンを受けるとか、自然となりましたよね。先生がここまでやってきなさいなんて言わなくても自分でやっていかないと気が済まないような感じで、それで「できないな、どうしようどうしよう」みたいな感じでしたよね。
——子ども時代を北海道で過ごされたのでしたっけ? 今回それを初めてお伺いして。転勤族だったんですね。
親の仕事の転勤で幼稚園の頃から札幌に住んでいて、小学校の4年生の3学期から北見市に移って5年生いっぱいまでいて、また6年生の時に札幌の同じ学校に戻りました。同じ学校の同じクラスに入ったので、古巣に戻ったと思いきや、周りのムードが冷たくてね、招かれざるとんがってたのがまた来やがったみたいな感じで(笑)。子ども心にかなり傷ついたのを覚えています。
そんなに社交的でもなかったのでしょうけれど、とんがってると、友達出来にくいので、ちょっと寂しい思いをしながら、中学1年生の1学期まで札幌にいたんですけれど、また親の転勤で2学期の時にこちら・・・最初は川崎に一回来て、3学期でまた杉並区に移るという・・・ということでまた中1の時に3回学校を変わってるんです。それがかなり苦痛で、しかも全部進度も違うし、教科書もやってるところが全部違うので…
——1年間で、何回もやった場所とやれなかった場所があるみたいな…
そうそうそう。こっちは一所懸命頑張ってキャッチアップしたんだけど、転校生というのはやっぱり「よそ者」と見做されて成績もちゃんと付けてくれない、そういう理不尽な思いもしたりして・・・やっぱり「よそ者」なんだよね、途中から入ってくるとね。そういうのはあってはいけないので、そこは強調して書いても良いかもしれない(笑)。
だから小学校から中学校にかけて多感な時期にアウトサイダーとしての気持ちを植え付けられてしまって、自然と自分一人でなんとかしなくちゃいけないという思いが強くなって、そうすると自分の好きなことに、より集中しやすいじゃないですか。友達がやってるから自分もやるんじゃなくて、自分がやりたいからこれをやるんだみたいなところは自然と出来ていってしまって。そういう意味では友達を作るという意味ではマイナスだったけど、自分自身の、何かこう極めていくという姿勢は十分身についたので、何が災いになって何が上手くいくかわかりませんね(笑)。
——先ほどのアメリカでのご経験などで見られた、たくましさみたいなものも育まれましたか?
そう、さらにアメリカで揉まれました。アメリカはもっともっと個人主義で、とんがっている人が、さらに削られる恐れもあった。それに私のケースの場合にはボストンに行った間だけでラボが3回も変わっているし(笑)。チョムスキーに出会うまでに3回変わっているので、相当な・・・今から見れば普通の苦労でしょうけど・・・最初の目論見というか期待感からすれば相当キツかったですね、メンタルには。
しかも単身アメリカに向かって縁故がある訳でもない。奨学金を最初はもらったけれど、続かないし、グリーンカード取ってとか、そういう決断も含めてみんなモヤモヤっと重なっている中での2年間だったので、アクロバット的にやっている間に日本に帰る話が舞い込んできたから、もうなんというか、激動でしたね。
Q4:
いつ頃から、どのようにして脳科学にご興味を持たれたのでしょうか?
——ではちょっとお話を戻しまして、脳科学にご興味を持たれたとさっきお話があったのですけれども、そもそも物理学科に至るところをお伺いして良いですか?
そうですね、高校の頃、朝永振一郎先生のお弟子さんの物理の先生がいらっしゃって、湯川朝永という日本の物理学を戦後切り開いたパイオニアの薫陶を間接的に受けて、素粒子物理学とかね、宇宙物理学とか、そういうものに好奇心が満たされていく訳です。
で、当時の私にとってのヒーローは、当時もう亡くなっていたけどアインシュタインとか湯川先生、朝永先生だったので、とにかく3人の書いたものを読むというのが日課になっていました。一方でオーケストラ部にはいたけど、当時楽器は習ってなかったので、進学を考えるという以上に、もう本の世界に、孤独の世界に、のめり込むという感じでいました。
中学1年生くらいの時には、将来の夢を書く作文みたいな時にはハッキリ「科学者になりたい」とは書いたんですけれども、方向性が決まったのは高校から大学にかけてです。でも研究者になるんだということに対して、周りの誰もが、言うまでもなくみんな反対でした。特に理学部とか物理とかで周りにいないですから、そんな霞みたいなことで生業になるはずはないという風にみんな言うので、そう言われれば言われるほど、「やってみよう」という気が強くなるという(笑)。
——てっきりご両親のどなたかとか、親戚とかに、研究者がどなたかいらしたのかなと勝手にイメージしていたんですけれど。
いないですね。0というよりマイナスでしたね。
親父は工学系でしたが、理学部というのはまた性格も違って、要するに実用的になるかどうかわからない、基礎的なサイエンスなので、それを黙々とやるというのは浮世離れしているというイメージは当時は今よりももっと強かった。
——高校の時、研究者にご自分がなれるかということを考えた時に、アインシュタインの書かれたものを全て読破できたらなれる、みたいなことをお考えになったと伺ったように思うのですが。
そうなんですよね。ウチの大学は1年生の段階では学部は決まらないので、物理学を目指すにあたって、アインシュタインの論文を自分で読んで、自分で分かったと思ったらその道に進学しようというふうに自分で決めていたわけね。
だから自分でテーマ設定をやって、今から考えればかなり無謀な、決してお勧めできない、ただ自分が非常に狭い見識と偏った興味だけで設定したゴールで、それでおそらく確率的にはクリアする可能性はかなり低かったと思うのですが・・・ただ幸か不幸か読んでものすごく分かった気がしてしまった・・・。この感動はちょっと人には言えないですね。
アインシュタインの論文って幸いなことに非常に分かるように書かれているんですよ。もう何と言うか、ある意味音楽の最も均整の取れた、しかも美しい作品と同じように、アインシュタインの論文は書かれていたので、それをモデルにしただけで幸いでしたね。そうじゃなかったらもう振り落とされていたかもしれない。だけとアインシュタインという人は本当にすごい人で、自分の思考過程を含めてわかるように書いているんです。しかも一般の人が読める入門書まで書いていて、それは金子務先生が訳された本が今でも手に入ります。すごいことなんです。その本は全く数式を使っていないので、まあある意味小学生でも読めるし、ガッツがあれば中学生でも読めると。
——入門書としてアインシュタイン自身がちゃんと編纂したものがあって、頑張れば小学生でも読める・・・。
そう、はい。私は10歳向けの日曜学校をやってるんですけれども、それを使ってます。
——これは是非Fruitfulでも紹介していただきたいですね。
そうですね。
——先生は、たとえばアインシュタインのことを研究したいと思った時に、アインシュタインについて書かれたものではなくて、アインシュタイン自身が書かれたものに当たるということをすごく大事にされていたと伺ったのですが。
そうですね、それは自分で到達したんですよね。そのまえに、アインシュタインという名前のついている本は片っ端から読んでたんだけど、モヤモヤして。分かりやすく書いていて色んな例え話があるのに、何故そういうことを考えたのかとかいう、一番自分が知りたいことが何も書かれていなかった。
ところがアインシュタインは自分でそれをやったから初めて自分は何故そう考えなくてはいけなかったのかということが極めて簡潔にハッキリと目に見えるように書かれていて、その違いが、クリアさが違うんです。
だからたとえばモーツァルトの曲を子ども向けに編曲しました、さあ弾き易いでしょう、みんなで弾いてみましょうというのと全然違うんですよ。モーツァルトが書いた、そのままが弾けるという感動なんですね。それは本当に、リライトしただけで、やっぱり変わってしまう。だから芸術の本物に触れるのと同じような感動が、本の世界や学問の世界でもあるんです。
——楽譜でも20世紀くらいの楽譜って、本人が元々書いたことと編集者が書き入れたことが区別なく書かれているものが結構ありますが、それを今は楽譜も原典がこうで、書き足したのはこれだというふうになっていますね。
明確にね。スラーですら元があったのか無いのか、強弱記号は一体誰がつけたのかがわかるように編纂されるのが今では常識ですが、私の子ども時代はまだそんなのは無かったので、本当に版が変わる度に翻弄されますよね。
同じフレージングなんですけれども全く違った表記がなされていたり・・・これはベートーヴェンの自筆譜とか見ているとかなり揺れもあって、そこら辺も同じフレーズが出てきたら同じ表現はしないほうが音楽的だというようなメッセージだったりするので、非常に難しいです。
同じフレーズで同じボーイングのはずなのに、スラーのつき方が違っているというのは、かなり悩ましいですよね。でもやっぱりそういうのもオリジナルを作った人の強みなので、やっぱり原典というものに戻ってみた時に、色々、自分の疑問がちゃんと答えが出てくるのとよく似ています。
アインシュタインではそういうことを高校生時代にもう体験したので、大学に入ったらオリジナルの論文を読みたいという気持ちになって、ドイツ語はまだ習いたてで無理だったけど、英語版と日本語版の頼りで読んで、その後ドイツ語版を読めるようになって、そうするとベートーヴェンの自筆譜とか、書簡とかまで、ドイツ語で読めるようになるわけです。そうすると翻訳と全く違ったkraftとか、言葉のすごさとか、そういうものがどんどん頭に入ってくる楽しさがあります。
当時大学院はドイツ語の試験がありましたけど、楽々クリアでしたね。だから趣味が高じて、ドイツ語の勉強をしなくても、ひたすら読んでたので、まあ今からいえばやっぱりドイツ語の音を聞くべきだったと反省しいているんですけれど、文字の世界からもずいぶん分け入ることはできたのは楽しかったかな。
酒井先生に脳に関する質問をしよう!
この記事は皆様からの質問で成り立っています。たくさんの質問をお待ちいたしております!
プロフィール
酒井邦嘉(さかい くによし)
専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。1964年、東京都生まれ。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻 教授を兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞など受賞。著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)、『脳とAI』(中公選書)、『科学と芸術』(中央公論新社)、『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など。

酒井先生の研究に関する記事はこちら
(マンスリースズキより)
スズキとの共同研究を進める東京大学酒井邦嘉先生の新刊書
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/sakai2024.html

新刊『勉強しないで身につく英語』を発売
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/eigo.html
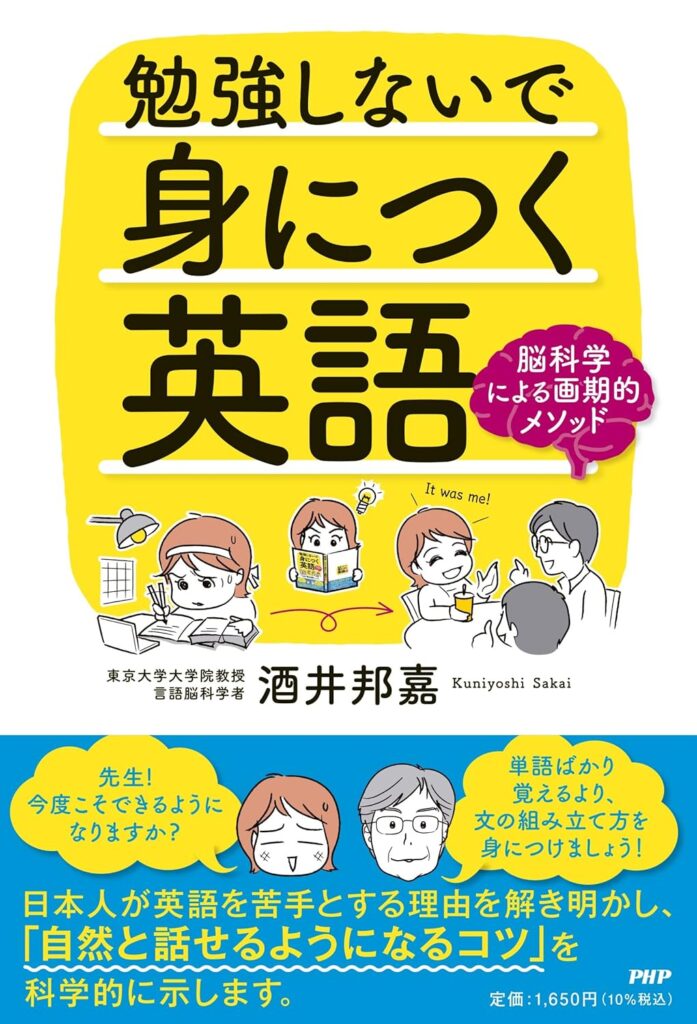
音楽の有効な習得方法を脳科学で実証
ー練習方法の違いにより左脳と右脳の活動が変化ー
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo5.html
東京大学との共同研究の論文を発表
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html
共同研究を話題に、毎日メディアカフェ
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/220510-2.html
酒井邦嘉先生の東京大学教養学部報内のWeb記事
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/648/open/648-1-01.html

今回も個性的な質問揃いです!『脳にはさわられた感覚がありますか?』『楽器での記憶定着のコツは?』『ニューロンの出した信号が、どのようにして音楽表現につながっていくの?』『コンサートで緊張しなくなる方法は?』の4本です!

今回は「アナログvsデジタルをテーマに、どちらが人間の能力をより引き出し高めてくれるか」「睡眠は学習にどう影響するか」など4つの質問にご回答くださっています。

今回の質問は『興味のない事はどうするとすぐに覚えられますか?』と『ぼんやりと特に何もしていないときの脳活動、デフォルトモード・ネットワークの子どもの脳への影響について教えてください』です!

今回の質問は『年齢が増えるとニューロンも増えるのでしょうか?』『ニューロンの数は決まっているのですか?それとも人によって違うのですか?』『ニューロンを増やすのに有効なことはありますか?また、ニューロンの働きに悪い影響を及ぼすものはありますか?』です。興味深い質問ばかりです!

酒井先生が脳に関する皆さんの疑問にお答えくださるシリーズ。今回の質問は『頭の良い・悪いって、脳科学的にはどういう状態のことを言いますか? 例えば、計算の得意な人と苦手な人の脳の違い、音楽や楽器演奏の得意な人とそうでない人の脳の違いはどんなところにあるのでしょうか?』

読者の皆さんからの質問に酒井先生がお答えくださるシリーズ。今回は①ニューロンはどのようにスケッチしたのか? ②ニューロンひとつひとつの働きは? の2つの質問への回答です!

脳が持つ最大の特徴、それは使い方、育て方によって機能がカスタマイズされ続けること!この驚くべき能力「可塑性」について、スズキ・メソードと共同研究をしている脳科学者、酒井邦嘉先生が解説してくださいます。