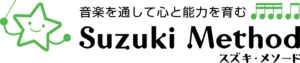
連載第6回 「脳の能力を引き出すには」
東京大学教授(言語脳科学者)
酒井 邦嘉
この連載では、年齢とともに脳やその能力がどのように発達していくのか、脳のそれぞれの部位がどんな働きをするのか、その仕組みなどを初歩から解説しています。今回もたくさんの質問を頂き、嬉しく思います。寄せられた中から関連したものを選んで、それに答える形で進めていきたいと思います。脳に関するいくつかの質問については、私の近著である『デジタル脳クライシス』(朝日新書、2024年)の中に答えやヒントが見つかりますので、あわせてお読みください。

Q1:
小2男子ピアノ科の母です。現在は、何かと思考力と言われますが、読み書き算術などやはり昔のやり方は優れていると感じます。日本人の遺伝子、環境などに合う教育法など脳の視点からありますでしょうか? また、iPad教育など学校教育も変化しておりますが、アナログの大切さを感じます。時代の変化を否定している訳ではありません。避けては通れない事ですが、脳が心配です。
A:
『デジタル脳クライシス』でも書いたこととも関係しますが、大切なご指摘なので、改めて整理してお答えしたいと思います。
まず、アナログ機器とデジタル機器を比べてみましょう。紙の本と電子書籍、万年筆(まんねんひつ)と電子ペン(スタイラス)、そろばんと電卓、ピアノとキーボード、楽器とシンセサイザー、といったもので、具体的に比較してみてください。総じて、前者のほうが優れているのですが、それはなぜでしょうか。
それぞれ具体的な特徴は異なりますが、そうしたアナログ機器が持つ特徴の根底にある共通性を正しく捉(とら)えることができれば、立派な答えになります。
たとえば、紙の辞書と電子辞書について考えてみましょう。見出し語にたどり着くまでは電子辞書のほうが確かに早いのですが、複数ある意味から適切な語義(ごぎ)や用例を見つけるには、紙の辞書を使うと圧倒的に早く、そして正確になります。それは紙面の全体を見渡すという「一覧性(いちらんせい)」を利用できるためです。
サイズの大きい紙の辞書では、目につきやすい品詞(ひんし)や番号などをとびとびに探すことができます。また、必要な情報が目に飛び込んでくるようなことがよくあるのですが、それは、脳が特徴抽出(とくちょうちゅうしゅつ)の能力を発揮することで、自動検索を実現しているのです。
一方、電子辞書やスマホでは、小さな画面で行きつ戻りつ(スクロール)しているうちに見落とすことが多くなります。
つまり、電子辞書は見出し語の検索だけを重視して実用化されたため、辞書の本来の機能はまるで再現されていないのです。先日の収録でインタビューをしてくださった方が、学生時代に英語が苦手で友人に相談したところ、「電子辞書や翻訳ソフトはやめる必要があるよ」と言われたそうです。その人は、良い友人を持って幸運でした。
このように、アナログ機器とデジタル機器では、表面上は同じような働きを持つように見えたり、多機能なデジタル機器のほうが便利で楽なように感じられたりしますが、実際にはアナログ機器のデザインのほうが脳の能力を引き出しやすくなっており、表現の幅も広いものです。
そもそも、開発されて数年から数十年ほどしか経っていないデジタル機器が、何百年も人々に使われてきたアナログ機器を簡単に追い越せるはずはありません。また、デジタル機器はソフトウェアの更新(アップデート)が当たり前になっていますが、完成度の高いアナログ機器(たとえばストラディバリウス!)では働きを維持するための調整以外は一切必要ありません。「新しければ良いもの」という誤った先入観(せんにゅうかん)は禁物(きんもつ)なのです。
以上のようなことに気づかず、人工知能(AI)や翻訳ソフトに頼り続けていたら、脳の思考力や判断力を成長させる機会を失ってしまいます。
脳が持つ基本的な能力は人間すべてに当てはまるわけで、日本の文化や環境などに限った問題ではありません。楽器を演奏できるみなさんは、「音楽」という世界規模の芸術を通して、「アナログ楽器」の素晴らしさを知っているはずですね。

Q2:
睡眠と脳の関係について知りたいです。お勉強とピアノを効率よく練習するおすすめのタイムスケジュールはありますか?
A:
脳の能力を引き出す鉄則(てっそく)は、 「よく学び、よく眠れ」です。
睡眠は脳の疲労回復の効果だけでなく、脳が学んだ情報を整理する役割があると考えられています。たとえば「スキーは夏にうまくなる」と言われるように、長く練習を休んでいた後に不思議なほど技術が上達することは、確かによくあるのです。ですから、十分な睡眠をとっていれば、自分の好きな時に練習してまったく問題ありません。
ただし、新しいことを学んだり、難しい曲を練習したりするには十分な時間が必要ですから、学習や練習に決して「効率」を求めてはいけません。保護者の方は、「うちの辞書に『効率』の文字はない」と指導してください。
Q3:
毎日1時間練習するのと週に1回7時間練習するのとでは、トータルの時間は同じですが、上達(弾きやすさなど)に違いはありますか?
A:
一つ前の質問とも関係しますが、視覚などの基本的な知覚(ちかく)に関わる学習(「知覚学習」と言います)を定着(ていちゃく)させるには、レム睡眠が必要であるという論文があります。「レム(REM)」というのは、rapid eye movement (急速眼球運動)の略号で、睡眠の周期の一部分である浅い眠りを表します。その時、体の力は抜けているのに眼が速く動いて、起きているときのような脳波のパターンを示すのです。
レム睡眠では、交感神経のほうが副交感神経よりも優位になっており、夢を見ていることの多い状態です。逆に、副交感神経のほうが交感神経よりも優位となるノンレム睡眠は、深い眠りに対応します。
レム睡眠が学習に及ぼす効果を考えれば、全体の時間は同じでも、睡眠をはさむことで練習の定着や上達に違いが出てくると言えます。そうでなくとも長時間の練習には体力と集中力が必要ですから、30分から1時間ごとに水分と栄養を補給して、休息を取るようにしましょう。

Q4:
酒井邦嘉先生の過去の発言で「input[入力]するという観点からいうと読む聴くも一緒だ」という発言があったのですが、[中略]自分なりの記憶の理論の根底をなすものなので確認したくご連絡いたしました。
A:
脳にとって、読むのは視覚(しかく)の入力、聞くのは聴覚(ちょうかく)の入力です(『デジタル脳クライシス』にも解説を書きました)。ただし、読むための文字や楽譜は、音声や楽音と比べれば、圧倒的に情報量が乏しいので、脳の想像力を使って正しく補う必要があります。この時、理解や記憶が想像を助けることで、より適切な「解釈」ができるようになります。
その意味で、読書や読譜は想像力のトレーニングとして最適なのですが、曲を耳から覚えるスズキ・メソードのほうが自然習得の理想に近いと言えます。
編集部より
今回の酒井先生のお考えに即し、印刷用PDFを作成しました。是非お教室やご家族でご活用ください。
酒井先生に脳に関する質問をしよう!
この記事は皆様からの質問で成り立っています。たくさんの質問をお待ちいたしております!
プロフィール
酒井邦嘉(さかい くによし)
専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。1964年、東京都生まれ。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻 教授を兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞など受賞。著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)、『脳とAI』(中公選書)、『科学と芸術』(中央公論新社)、『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など。

酒井先生の研究に関する記事はこちら
(マンスリースズキより)
スズキとの共同研究を進める東京大学酒井邦嘉先生の新刊書
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/sakai2024.html

新刊『勉強しないで身につく英語』を発売
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/eigo.html
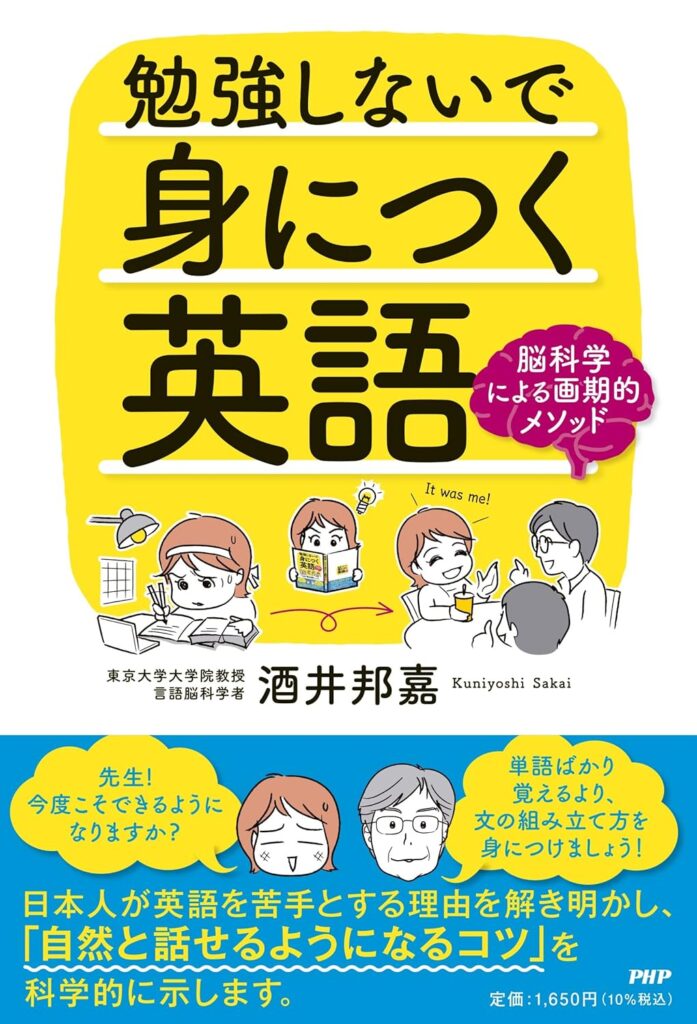
東京大学との共同研究の論文を発表
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html
共同研究を話題に、毎日メディアカフェ
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/220510-2.html
酒井邦嘉先生の東京大学教養学部報内のWeb記事
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/648/open/648-1-01.html

今回の質問は『興味のない事はどうするとすぐに覚えられますか?』と『ぼんやりと特に何もしていないときの脳活動、デフォルトモード・ネットワークの子どもの脳への影響について教えてください』です!

今回の質問は『年齢が増えるとニューロンも増えるのでしょうか?』『ニューロンの数は決まっているのですか?それとも人によって違うのですか?』『ニューロンを増やすのに有効なことはありますか?また、ニューロンの働きに悪い影響を及ぼすものはありますか?』です。興味深い質問ばかりです!

酒井先生が脳に関する皆さんの疑問にお答えくださるシリーズ。今回の質問は『頭の良い・悪いって、脳科学的にはどういう状態のことを言いますか? 例えば、計算の得意な人と苦手な人の脳の違い、音楽や楽器演奏の得意な人とそうでない人の脳の違いはどんなところにあるのでしょうか?』

読者の皆さんからの質問に酒井先生がお答えくださるシリーズ。今回は①ニューロンはどのようにスケッチしたのか? ②ニューロンひとつひとつの働きは? の2つの質問への回答です!

脳が持つ最大の特徴、それは使い方、育て方によって機能がカスタマイズされ続けること!この驚くべき能力「可塑性」について、スズキ・メソードと共同研究をしている脳科学者、酒井邦嘉先生が解説してくださいます。



