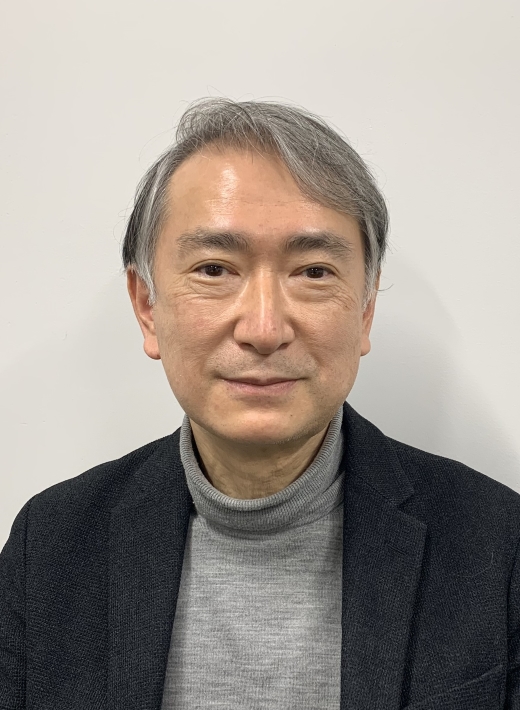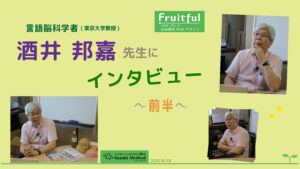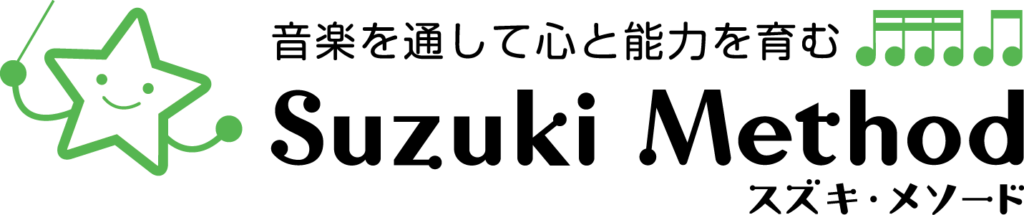
第11回 楽器の演奏・練習と子どもの発達
東京大学名誉教授
精神科医師・医学博士
佐々木 司
今回と次回で、バイオリンやチェロ、ピアノ、フルートなど、楽器の演奏や練習が子どもの脳と能力、メンタルの安定、さらにメンタルと関係の深い仲間作りにどう影響するかについて考えたいと思います。今回はまず、子どもの脳・能力との関係について、これまでの研究の結果を踏まえてお話いたします。なお本コラムは主に思春期について扱ってきましたが、今回は思春期に限らずご紹介したいと思います。
多くの複雑な要素からなる楽器演奏
具体的な「脳・能力」の話の前に、「楽器を演奏する」という動作がいかに多くの要素で成り立っているかをまず考えてみたいと思います。楽器演奏とその練習が、子どもの能力にどう影響するかをイメージしやすくなるからです。
一般に楽器の演奏では、右と左の手・上肢に全く違った動きをさせる必要があります。また手・上肢に加えて体幹や下肢、つまり体全体の動きと姿勢の保持を連動させる必要があります。ちなみに下肢については、ピアノのペダルのように、上肢と同様に動かす必要のある楽器もあります。
そのように体のあちこちを連動させて動かすことは、それだけでも難しいのですが、楽器演奏では、リズムやテンポに合わせて、正確なタイミングで動かす必要があります。加えて弦楽器や管楽器では、自分で正確な音程を作りながら演奏を続ける必要もあります。そのためには、自分の作る一連の音を聞き、それを記憶しながらそのあとの音を作り続けなければなりません。
感情と視覚情報も統合
さらに楽器演奏では、曲が醸し出す気持ちの表現が重要です。このためには曲ごとの違いは勿論、細かいフレーズごとにふさわしい音色と音の大小、その変化を、曲の流れにともなう気持ちの変化に沿ってコントロールしなくてはいけません。
さらに多くの場合(少なくとも暗譜するまでは)、これら全てを、楽譜を見ながら同時に行う必要があります。リズムについては各音の長さの割合や強弱を、無意識のうちに計算・理解することも必要です。
普段子どもたちが何気なく練習しているように見える楽器演奏ですが、その要素と組み立てについて改めて考えてみると、想像もつかないほど複雑なことを行っていることが理解できます。人間の動作・行動の中で、これほど多くの要素が複雑に絡んで構成されているものは余りないかもしれません。
多数の脳領域を駆使
このように複雑な動作を行うには、それに対応する膨大な数の脳領域を同時に、かつ複雑に使う必要があります。
「音楽で使う脳領域」と言うと、まずは「聴覚」に関わる脳領域が頭に浮かぶかも知れませんが、それだけではありません。視覚、触覚(楽器、鍵盤、ペダル、弓にふれますから)も使われます。
そして当然ながら筋肉を動かす脳領域が使われます。同時に情動と記憶の中枢(その曲を思い出し、一瞬前まで自分が作ってきた一連の音とそれが作り出す感じを記憶し続けないと、演奏はできません)が使われます。リズムや曲のフレーズを作るのに必要な空間や時間の感覚に関わる脳領域も使います。
音の強弱、また曲に合った音、良い音を作るには、筋緊張の微妙な調整が必要ですが、これにはいわゆる大脳皮質以外の多くの脳領域(大脳基底核など)を駆使する必要があります。上肢と体全体の複雑な動きをコントロールし、動きを学習する脳領域も駆使されます。小脳などです。
最後に、これら全ての脳活動を「曲の演奏」という形にコンロトールするための脳領域(大脳前頭前野など)も活発に使われます。楽器演奏とその練習では、これらの膨大な数・大きさの脳領域がフル稼働すると言って良いでしょう。
各領域の接続の高度化
楽器の演奏では、これらの脳領域が個別に活動するわけではありません。多くの領域が同時に、連携・協調しながら働かないといけませんので、領域間のスムーズな接続も必要です。楽器の練習を続けて上達するということは、それらの接続が最適な形で強化されることでもあります。
大脳は左右の半球に分かれていますが、演奏では両手を使いますから左右の接続も当然強化されます。大脳の各領域間は勿論、大脳と小脳、さらには情動に関わる脳の中心部とそれらの領域、それぞれの連携・接続も強化されると推測されます。
脳と能力の変化の実際
ここからは、楽器演奏とその練習が子どもの脳や能力にどう影響し得るか、実際の研究結果を見ながら考えたいと思います。
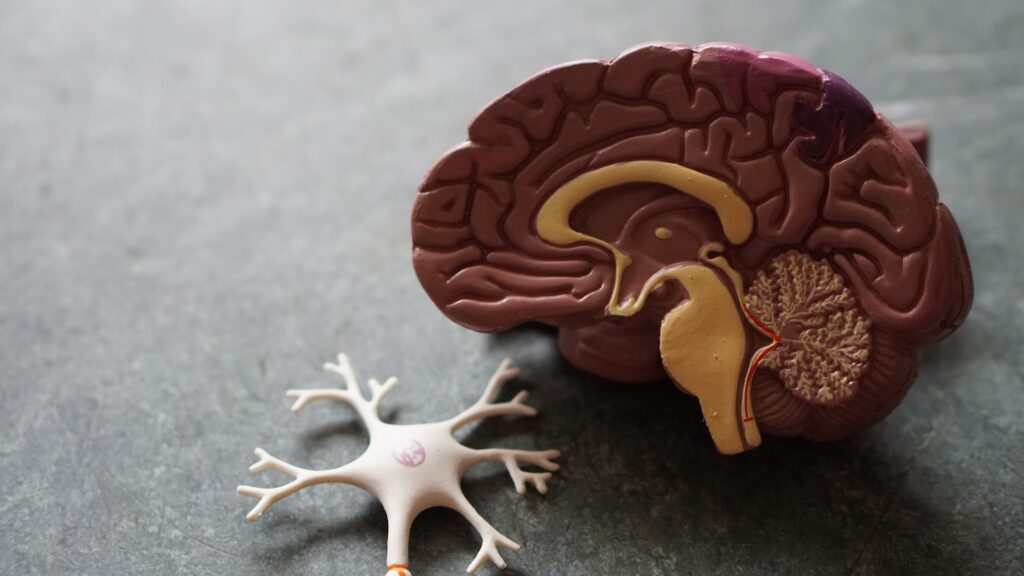
左右の大脳の接続
大脳は左右の半球に分かれていて、両半球は神経線維の太い束(脳梁と呼びます;上の写真では「つ」を左右反対にした形の黄色の部分)で結ばれています。この束が無いと左右の大脳はバラバラにしか働けませんので、大脳全体が統合的に機能する上で大変重要な部分です。楽器演奏では左右の手・上肢の違う動きを連動させ続けますので、脳梁も強化されるのではと推測されます。
実際、6歳児を楽器の個人レッスンを受ける群と、同じ程度の時間、歌やドラムや鈴を使った演奏のグループレッスンを受ける群に分けて追跡した研究では、15カ月後には脳梁の大きさが楽器の個人レッスンを受けた群の方が大きくなっていることが示されました。
手の動きに関わる脳領域
また大脳の右側では、手の運動に関わる運動野が、聴覚野とともに、楽器の個人レッスンを受けた群の方が大きくなっていました。ここでは「右側」という点が大事かも知れません。
大抵の人は右利きなので右手を多く使います。体の右側は脳の左側が、体の左側は反対に脳の右側がコントロールします。したがって右側の脳で、手の運動野が大きくなったということは、普段使わない左手を使ったこと、つまり楽器の訓練により右手だけでなく左手もしっかり使ったことの成果と考えられそうです。
ちなみに楽器の演奏では単に筋肉を動かすのではなく、繊細な動きが必要です。音楽教育を受け始めた5-9歳の子どもと、そうでない子ども(家庭の環境や知能のレベルは一緒)を14カ月追跡した研究では、音の識別能力に加えて繊細な運動の能力も、音楽教育を受けた子どもの方が高くなっていました。
読む力との関わり
音楽も言語も聴覚情報の処理がその根本にあります。したがって音楽の訓練が言語に関係する脳の領域とネットワークに作用する可能性が考えられるのですが、実際の研究でもそれを支持する結果が得られています。
その1つは読む力への影響です。音楽も言語も、聴こえてくる一連の音の構成を脳内で解析し、意味のある繋がり(あるいは固まり)として把握するという点で共通しています。これをメロディー、あるいは言葉として理解していくわけです。
一連の音の理解にあたっては、音楽は勿論、言葉でも、音の高低の弁別やリズムの把握が判断材料となる点も共通しています。
外国語の習得と音楽の能力との関係
音楽の訓練は、読む力以外の言語能力、具体的には言葉の流暢性、言語記憶、さらには外国語の習得にも良い影響を及ぼす可能性があります。
外国語の習得については、大人を対象とした研究で、音楽の能力と外国語のうまさとが関連することが、子どもを対象とした研究では、外国語の発音の正確さと音楽のスキルが関連することが報告されています。
ただこれについては、元々音の処理に関わる能力の高い人が、音楽でも外国語の習得でも有利だからという可能性もあります。「音楽教育の成果」かどうかは、別の方法での研究結果を待つ必要がありそうです。
無理にやらせれば良い訳ではない
ここまで、楽器の練習などの音楽教育が脳の発達や言語の発達に影響する可能性があることを述べてきました。ただ現時点ではまだまだ研究の余地があり、全ての結果が確定されている訳ではありません。今後さらに多くの研究結果が報告されると思います。
また音楽教育の研究は、動物相手と違って教育する群・しない群に子どもをランダムに振り分ける訳にいかない場合が多く、方法論上の限界もあります。結果の解釈では、その点も注意しておく必要があります。
もう1つ注意してほしい点は、楽器の練習に様々な効果がありそうだからと子どもに無理強いしても、同じ効果が得られるとは限らないことです。楽器の練習が成果をあげるには、そもそも楽器の練習を子どもがやめてしまわないためには、「練習して良かった」と子ども自身が思えることが大前提です。
勿論、練習には苦しい時もありますが、「今日のレッスンのために1週間練習を頑張って良かった」と思うことがなければ、練習は長続きしません。これは次回お話する予定のメンタルへの影響でも大いに言えることです。孫に習わせている身として自戒の念も込めて、このことには充分気をつけたいと思います。
佐々木司(ささき つかさ)
東京大学名誉教授、公立学校共済組合関東中央病院メンタルヘルスセンター長、精神科医師・医学博士。小学校入学後よりスズキ・メソードでヴァイオリンを習う。東京大学医学部医学科卒後、同附属病院精神科で研修。クラーク精神医学研究所(カナダ、トロント市)に留学。東京大学保健センター副センター長、同精神保健支援室長(教授)、同教育学研究科健康教育学分野教授などを歴任。思春期の精神保健、精神疾患の疫学研究、学校の精神保健リテラシー向上などに取り組んでいる。日本不安症学会副理事長、日本学校保健学会常任理事、日本精神衛生会理事を兼務。