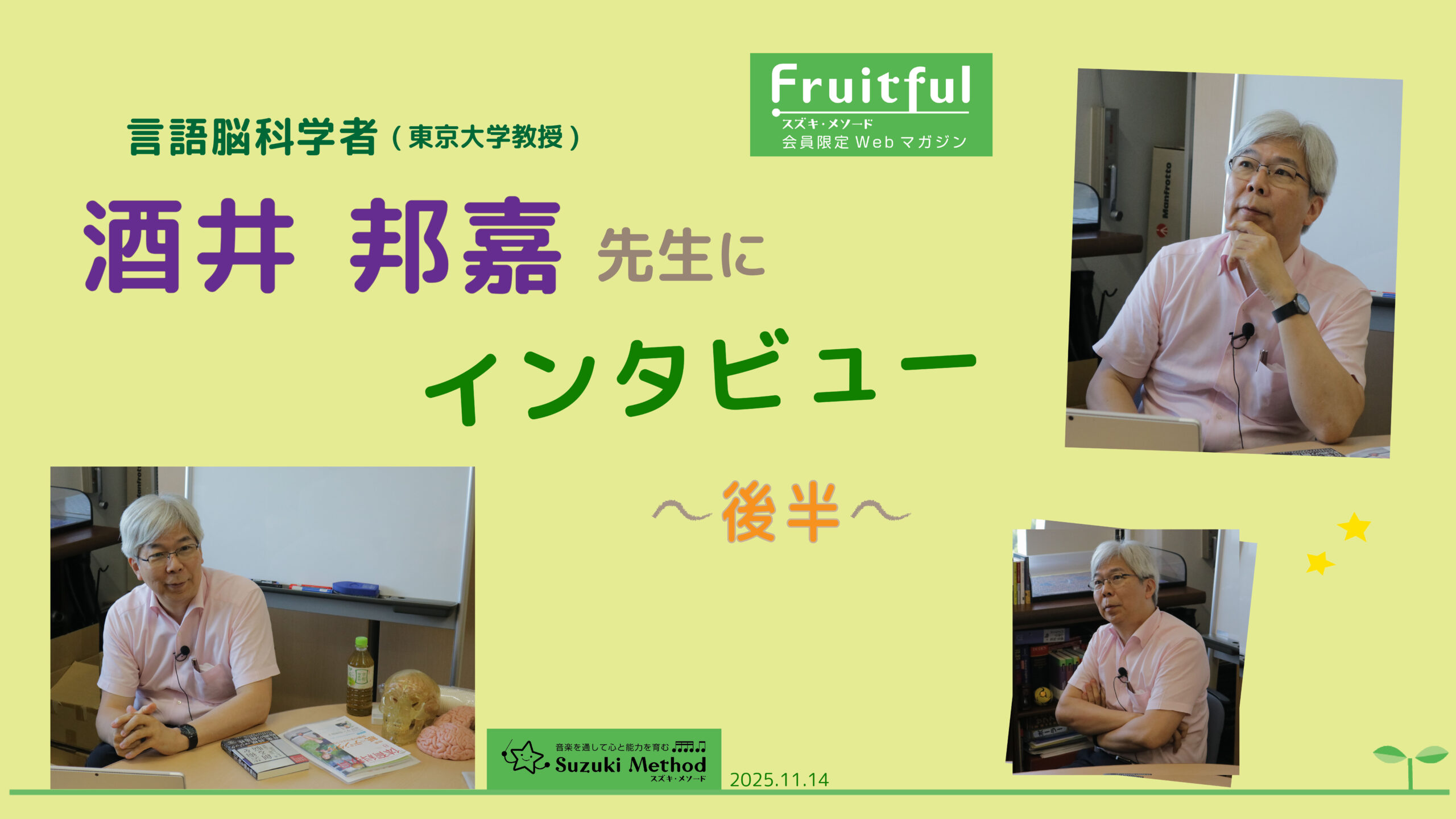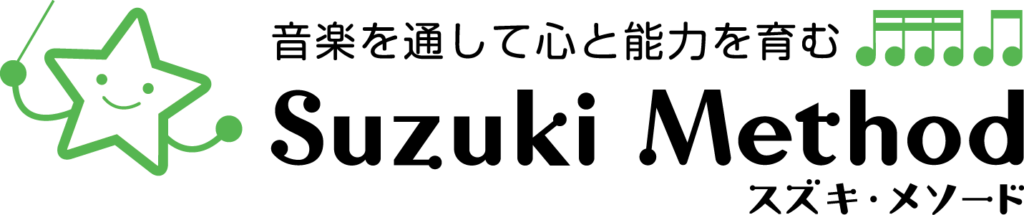
特別編 酒井邦嘉先生にインタビュー[後半]
東京大学教授(言語脳科学者)
酒井 邦嘉
今回の「脳と能力」は前回に引き続き、まさに東京大学とスズキ・メソードとの共同研究を実際に行っている日に、著者である酒井邦嘉先生の研究室にお邪魔し、共同研究について、そして先生のパーソナリティについてお伺いしました。
Q6:
大変お忙しい酒井先生の、一日のおおまかなスケジュールを教えてくださいますか?
そうですね、ほとんど自分で意のままにならない予定で不規則に決まってしまうので、(学生さんとの)研究の相談の時間をまず大事にして、そのあとは講義とか会議とか、講演とか取材とかの時間が入ってきますね。残った時間で読書とか執筆とか、いう感じになりますね。で、夜の時間はできるだけ楽器を弾きたいなと(笑)。
——これだけお忙しい中で、夜はお時間を決めて楽器の練習をされているんですか?
そうですね。ただ見たいテレビとかあったら、そっちを優先する場合もありますけど(笑)
マンション住まいなので8時台くらいから9時まで練習という感じにしています。でも気が向いたらちょっと夕食後にやり始めるとか、そこら辺は状況に合わせてなんですけど、出来るだけ楽器に触りたいな、とは思っています。
Q7:
先生の音楽との出逢いと、普段の生活の中でどのように楽しまれているか、それからこれまで取り組まれた楽器についても教えてください。
ヴィオラを始めたのは楽器を買った10年ほど前ですかね。スズキの共同研究が始まった頃です。
——指導者研究会にいらしていただいた時に控室でヴィオラを弾いていらして!
はい、ヴィオラを持ち込んだんです。オーケストラをやっているとヴィオラが暗い音であるとか、どうしても目立たないとか、なんかそんなイメージだったんですけれど、僕が出会った楽器がすごく明るくて開放的なイタリアンで、すごくソロの楽器として響く感じが楽しくて。だからヴィオラをアンサンブルの楽器としてではなくて、ソロの楽器として見なすようになって、自分で弾きたい曲をやっては時々レッスンで見てもらったりしています。
ヴァイオリンはメインの楽器として、大人になって20年前くらいからレッスンを再開しました。それまでは我流で、すごい力が入って弾くような感じで勝手にやっていたのが、先生に就いたので全て取り払われて(笑)、いかに力を入れずに本当に弓の重さだけで弾くとか、そのあたりから大改造されて・・・今までやってきたのは何だろうと思うくらい一度バラバラになって、またそれを立て直して、というのが20年くらい続いてますね。リハビリみたいな感じもあるんですけど。それでいろんなことが見えてきたというのもありますよね。
——最初にヴァイオリンをされたのが小学校3年生くらいのときで、スズキの先生ではない方にスズキの教本で教わっていらしたと伺ったのですが、どのような指導方針の先生でいらしたんですか?
連載にも書いたことがあるんですが、セブシックで指慣らしをしてスケールをして、スズキ教本という3本柱でした。セブシックは非常に機械的なので、先が見えない繰り返し、反復練習・・・音名は全てドイツ音名で言われて小学生だとさっぱり分からない・・CisがどうのこうのだとかCisとDisがどうなんだとか(笑)。ところがあんまり説明を噛み砕いていただけないので・・・札響の先生だったんですけど。北見に言っている間はブランクがあって、その間はテレビでNHKの『ヴァイオリンのおけいこ』を見ながら・・・ちょうどその頃ベートーヴェンのロマンスをやってたんじゃなかったかな、それで弾きたいと思って自分でさらったりしてました。その後、札幌に戻ってきてまた同じ先生に就いて小学生までやっていましたね。
——ではレッスンを受けていたのは、一旦は小学生までだったのですね。
そうですね。親に泣きついて中学でもやりたいと言ったんですけど、何故か頑として続けさせてもらえなかったので(笑)。そういう苦い思い出があって、それで一人で弾くことになってしまったのが長い目で見るとあんまり良くなかったわけですよね。中学、高校でも、特に大学まで続けていらっしゃる方が周りにいるということを、そのあと知ることになるわけですけれども、彼らが羨ましかったですよね。それもあって、大人になってから、自分で楽器を買ったのを機会に、本気でやりたい! と思って先生に就きました。
——高校はオーケストラ部でいらしたんですよね。
そうでしたね。ヴァイオリンを弾いていたんですけど。そこは本当に初心者から育てるというポリシーのところだったのですが、それでもみんな弾けるようになるのがすごいですよね!
管楽器とかはね、オーボエとか持っている人はいないのでフルートに持ち替えたりだとかしながら、オーケストラの曲をやってました。今ちょうど(BGMで)かかっているベートーヴェンの2番をやったのが高校2年生の時でしたかね。
——特にベートーヴェンのシンフォニーを弾く経験というのは、今ベートーヴェンがお好きになるきっかけというか入口にも・・・
なっていたでしょうね。シンフォニーを弾くというのは特別な感情がありましたしね。特に夏合宿ではずっと2楽章をやっていたのを今でも覚えていますね(笑)。難しいですよね! テンポ感なんかもやっぱりベートーヴェンの個性が現れてますよね、2番から。多くの人は3番(『英雄』)からと思うかもしれないけど、1番の清々しさから2番でかなり内省的になって、非常に深みが増してますよね。
——そのあとフルートをされて、今年からクラリネットをされているとのことですが、どういう経緯で手に取られたのでしょうか? 先生は新しいことに次々挑戦されるのがお好きというお話が先ほどもありましたが。
そうですね、フルートは11年くらいやって、ちょうど先生が変わるということになって、この先どうしようかな、と思っていたところに知り合いの方から、子どもさんがクラリネット始めたんだけど全然続かなかったので、楽器差し上げます、みたいな話があって。私の姪が音大でクラリネットやっていたので、チラチラは見ていたのですが、その時はまさか自分が吹くとは思っていなかったし、フルートも相当苦労したので・・・でもまあクラリネットは面白いんじゃないかと。
私、口笛吹けないんですね。フルート始める時に、口笛吹けなくてもフルートは吹けるでしょうかという質問からスタートしたのを覚えているんですけれど、「フルーティストでも口笛吹けない人いますよ」と言われて、安心して始めたら・・・やっぱりクロスフィンガリング(半音を出すための特殊な運指)とかはすごく苦労しました。あと音出しがね、フルートの音になるまでが大変なので本当に・・・。でも10年くらいやっていると流石に音が気持ちよく吹ける時が出てくるので、純粋な雑音の混じらない音を出すという感じが掴めてきました。
でもクラリネット、オーボエ系のリード楽器(吹く部分に薄い板=リードを仕込んで振動させることで音を鳴らす楽器)は流石にちょっと人工的で無理かな、と思って避けてたんですけれど、まあそういうきっかけがあったので、面白いかもしれないとフッと思い出して。
そしたらリードはやっぱり難しいんですよね! まずはリードを箱で買っても使えるのがあまり無いとかいうのは、すごく初心者にとって恐怖なんですよ。プラスチックのリードとか色々試してみたり、結局音が出るまで悩みますね。何が正しくて、何が自分では出来ないのか。
楽器の選択も同じで、安い楽器でまず始めればって、大人は思うんでしょうけれど、そうすると楽器が問題なのか、調整が行き届いていないのか、本人のアンブシュール(管楽器を吹く際の口の形や息の出し方など)とか奏法とか弓の持ち方とかが悪いのか、一体何が問題なのかが切り分けられないまま、ただ弾けない、吹けないというストレスを味わうだけになる。
だから楽器はある程度ちゃんと道具としてメンテナンスができるしっかりしたものを手に入れて、その上でちゃんと先生に就いて最初立ち上げてもらうというところが大事だなと・・・。クラリネットでもそれをやらなければいけないということを最初の1、2週間で悟って、フランス人の先生に就いて楽しく教えてもらってます。今までにないメソッドなのですごくスピードも速いんですけれど。
ヴァイオリンだけやっているとあまり右指が動かないじゃないですか、弓を持っているだけなので。だからフルートでクロスフィンガリングで苦労して、その筋トレがかなり大変なんですね。さらにクラリネットは右小指に4つのキーがあったりするので、最近やっとそれをブラインドでもスッと指が行くようになるという、それは非常に面白い体験ですよね。でもそっちに気を取られると口の方が吹けなくなるのですが・・・3月に初めて4月から本格レッスンだから3ヶ月くらいやりましたか・・・まあちょうどヴァイオリンでいうところの右手と左手の感じみたいなのをやっと克服して、スケールも半音階も吹けるようになったかな(笑)この過程を自分の頭で実証しています!
——すごい! お忙しい中で本当にすごいなと・・・
最初はずっとボーボーやってましたけど、そういうのが好きなんでしょうね。
——共同研究の第2弾で、複数の楽器をしていることが脳にどう影響するかというお話がありましたね。
それもですから頭のどっかの隅にあったんですね。
ヴァイオリンとヴィオラという関係性を考えてみると、フルートとクラリネットというのも良い関係性なんですよね。音域的にも楽器のレパートリーというか深みとか、どちらも後者の方がより低音側にシフトするんですが、奏法とか、音楽の求めている内容がガラッと変わってきます。
ヴァイオリン曲をフルートで吹くのはすごく楽しいですし、またさらにそういったイメージの既に湧いている曲をクラリネットで演奏してみると、また音質が全然違って、こんな音が自分から出るんだっていうのがすごい発見で面白いんですね。ヴィオラのあの渋い、でもちょっと明るめの音というのはクラリネットと重なったりもするので、そういう風に「音を作っていく」というのが、複数の楽器を味わうことで体験できることです。
本当は自分の脳を見てみたいんですけどね、何が起きているのか(笑)!
——本当ですね! もしも何か機会があったら是非!
Q8:
特にお好きな作曲家や、楽曲などありましたらお教えください。
——お好きな作曲家、ベートーヴェンについて先ほど少しお話が出たと思うのですが。
ベートーヴェンは高校時代、「貸しレコード」をもう毎週のように借りてきてましたね。その時に知ったのがベートーヴェンの晩年のカルテットで、全部で16曲ありますけど・・・まあ16という数もベートーヴェンが選んだに違いなくて、16って4×4なんですね。カルテットは4つの楽器で出来るじゃないですか。それを4かけると16になるから、亡くなるまでとにかく16は書きたかったんだろうなと思うし、ピアノだとその倍で32曲書いているでしょ。それからピアノコンチェルトは指が5本あるので5曲書くとか、まあなんかやっぱりそういう数にはこだわっているんだろうというエッセイを昔書いたことがあります。
だからベートーヴェンって非常に論理的で、しかも自筆譜見ると分かるんですけど、本当に美しく構造が整っているということを目指して書き直すということを厭わなかった人なんですよね。
モーツァルトは、自筆譜いくつか持ってますけど、もっともっと天才的で、頭で全部構成が出来てから書き始めるから、書くのが間に合わないって言っているくらいもう完成度が高くて、あとはもう書くだけみたいな感じ。流れるように。
だからほとんど修正の跡が残っていないのだけれど、ただ例外は「ハイドンセット(6曲の弦楽四重奏曲集)」で、「ハイドンセット」はハイドン先生に捧げよう、献呈しようと思ったので、めっちゃ手を入れてるんですよ。自筆譜にはそういう跡が残るから、完成形だけ見たのでは分からない、作曲家の作曲の過程というのは自分的には大好きです。
というのは、私が論文を書いたり研究したりしていく苦労の跡とも重なるものだし、それが目に見えるという意味では自筆譜というのは非常に大切な発想の源泉だし、背中を押してくれるようなパワーを持っています。
ですから私の自宅の書斎のちょっと背の低い本棚の書架3つ分は全部自筆譜で埋まっていて・・・どんどんと手を出すとキリがなくて、マーラーとか、メンデルスゾーンとかも皆出してるから、そこまで手を出すのは諦めて、当時はベートーヴェンだけ徹底的に出てるやつは全部手に入れてました。今でも時々新譜が出ると買ってますけど(笑)。
——やっぱり一人の人を研究したいと思った時には全部一回接したいというお考えがありますか?
いやでも自筆譜って半端ない値段なんですよ! 学生時代に大枚はたいて買って・・・今でも覚えているけどラズモフスキー1番(弦楽四重奏曲 第7番。ベートーヴェンのパトロンの一人ラズモフスキー公に献呈された、3曲のうちの一つ)だけで10万円もしましたから! 学生で出せるのかというほどの額を、アルバイトやって全部貯めて。そのくらいですよ、私の興味の無謀さというか(笑)。でも今でも宝物だよね!
それで不思議なことに気付くんですけど、ラズモフスキーの1番は最初にチェロからスタートする。あそこは実はメゾ・フォルテで書かれているんですね。ところが他のベートーヴェンの楽譜見ると気づくんですけれど、本当にベートーヴェンはね、そういう律儀な人だったから、メゾ・フォルテとかメゾ・ピアノとかそういう中途半端な指定は一切していないんですよ。唯一の例外なの! 見た途端にひっくり返りましたよ。「やった!」 みたいな感じで。大発見!
多分音楽家ではあんまりご存じないかもしれない。でも自分の目で見て確かめるって、これすごいじゃないですか。基本的にピアノとフォルテしか使わない人が、ここは悩みに悩んでメゾ・フォルテなんですよ。あそこはチェロだけでテーマが出るから、強すぎてもいけない、弱すぎてもいけない、これは中庸しかない、だからこれは今まで自分はやっていないけどメゾ・フォルテだという、それだけでも分かるじゃないですか、ベートーヴェンの思いが。しかもカルテットの歴史の中で、冒頭がチェロからスタートするというのは、それだけでも本当にこれは新しいぞ、ということを打ち出したラズモフスキー1番だから、やっぱりベートーヴェンが中期の一番脂ののっている時に、これまでに無い新しいものを作っていくという気概に満ちたものが見えるわけです。
だから完成された楽譜を見るとやはりちょっと味気ない。うん。それをすごく思います。
——自筆譜ですとインクの濃さとか、そういうのがありますよね、伝わってくるものが。
はい。そうそうそう。で、後から赤鉛筆で書き込んだりとか、せっかく綺麗に書いてるのに全部バッテンとかね。
それなのに月光ソナタの冒頭は本当に澄み切ってるのか全く無修正で、もうモーツァルト的ですよね。頭の中で完璧にあのイメージが浮かんで、これしかない! という形で書いて。だからもうその精神状態というのがやっぱり創作のすごく大切な一部になるっていうのは、誰に言われることなく分かりました。しかしこうやって喋ってると、終わらない(笑)。すみません!
——共同研究が始まった頃に鈴木鎮一先生の全集も出てるんですよとお伝えしたら、あっという間に先生は古本屋さんで全部お買いになったと嬉しそうに言ってくださったことにとても感動したのですが、機関誌の連載はそこから言葉を選んでくださっているのですか?
最近に出た冊子とか、愛に生きるだけで、本当に至る所に宝のような言葉が散りばめられているので、だからあの全集に手を出すまでもなく、その2冊だけで実はずっと今まで来ています。そろそろ全集に手を出そうかと思っていますが。レアな言葉を是非引っ張って来たいです。フッと本を開くとちょうど自分が考えていることとシンクロして、一つひとつの言葉に目が合う感じで、すごいです。
——言葉に目が合うというのは本当にそうですね。
だから、亡くなった方とも十分対話ができるんですよね。本はありがたいです。自分はそうやって過去にアインシュタインと対話してきたので、鈴木先生とでも同じように対話できるというのは最初から分かってたわけだから、ありがたいですね。
——鈴木先生は録音などを通して、演奏されている人の心とか、作曲者の心とかとも対話されてた部分もあるのかなと思うのですが。
オリジナルの録音を聴く、ヴィルトゥオーソの録音を聴くというときに、もちろんそれはどういう修練をしたかとか、練習している過程は見えないけど、でもやっぱりそこに到達した芸の極みは分かりますよね。
Q9:
現在、教育の在り方が急ピッチで変化しているように感じます。脳科学者である先生の視点から、お感じになることをお話しくださいますか?
そうですね、私はやはり人間を研究の対象にしていることもあって、人間らしいものとか、それを追求していくと、やはり行きつくのは「自然」というものなんですね。
だから楽器の奏法というのも、究極は自然な呼吸とか、自然なボーイングとか、結局そこに行き着くわけで、できる限り無駄な力を入れないとか、音楽の流れというのに余分な操作とか人為を加えないということも大切であるわけなので、そういう見方をしていると、機械的な音とか機械的な操作というものが、その対極になるんですよね。
機械というのは人間のいろんな部分を置き換えようとするわけだから、人間の所作が機械化されることによって、効率的で、間違いはなくなるかもしれませんが、そこに対して人間的な喜びを失うことにもなる。
特にAIが出てきてしまうと、今度は考える喜びとか文章を作る喜びが失われるわけなんですね。こうなったらもう音を出す喜びというのは何としてでも人間の手の中に留めていかないと、教育が大変なことになるだろうと。
いわゆるお勉強的なことはもうどんどん怒涛の如くこの数年で機械化されて、デジタル教科書にも置き換わるという動きの中で、やっぱり本当の教育を失わないという意味では、情操教育とか、鈴木先生のおっしゃった全人教育とかいうのが最後に最も教育で必要な砦として残るであろうと思いますね。そこが流されたらもう終わりだと思います。
そういう教育が学校で出来ないのなら、例えばスズキで楽器を教わるとか、そういうことが非常に貴重であって、そうしないと人となりとか、ものの考え方、それから簡単に出来ないことを長い時間をかけて出来るようにするという一番大切な部分が、デジタル機器を使った教育では損なわれてしまいます。
つまり、いくらでも手軽に楽をして頭を使わずに結果だけ出せば良いんでしょ、というふうになると、もう機械に頼るだけなので、もうネット上での情報を勝手に自分のものにしたつもりになる。自分のものと言っても、本当にそれを咀嚼できていれば良いですけど、そうじゃなくて表面的にコピーだけして、それをあたかも自分の作品であるかのように詐称して、宿題とか作文とか、そういうものもこなしてしまった挙句に、何も自分の脳も手も使ってないということになるんですね。それは一番怖い。要するに思考停止になってしまいますよね。
そうすると、手間がかかって10年もかけてやっと自分の弾きたい曲が弾けましたみたいな喜びというのが、どんどん短期的で短絡的で刹那的なものに置き換わってしまうという怖さがあります。だからやっぱりそういうことに気づいた以上はいろんな形で発信をしようかなと考えて、最近特にAIに対する批判をしています。デジタル教科書に対しても、パブリックコメントを含めて反対をしています。
紙の本で読むのと、内容が同じだったらデジタルタブレットで良いじゃないですかという意見に対して、自分たちも実験をやりましたし、それから最近は手書きに対する効果検証の実験も始めたので、やっぱり手で書いて、写して覚えるということの大切さを訴えたいです。
一瞬で画面で見りゃ速いでしょって、そりゃ速いけど何も頭に残らないということを考えて欲しい。書き写すだけでも非常に大切な学習法なんですが、それは例えば楽器を手にして楽譜を一瞬見ればすぐ弾けるようなものはないわけで、それは相当弾けてればまだ初見も効くでしょうけど、同じような意味で、見たらそれだけで頭に入る、記憶に残るなんてものはなくて、常に咀嚼しなきゃいけないわけですね。そのためには書き写すという学習の一番最初のステップであるはずのものが、もう多分学校ではできなくなっています。
全て情報になって、それをノートをとることによって確認して、自分でわかっていないことを自分で発見して、そこを補ってということは時間のかかるプロセスなんですね。そこを機械に頼った時点で、全てが軽くなるということですね。例えば自分で楽器が弾けないんだったら全部パソコンで楽譜を音声を出すことは簡単にできますけれど、それは自分の脳を使うという意味ではゼロなので、それが何か作曲した作品を発表するものだ、というふうに勘違いしたら、もう多分音楽自身が成り立たなくなりますよね。
もちろんそういう偶然や違った表現形式の音楽というのは模索はされてるでしょうけど、でもやっぱりバッハの時代から2~300年すでに続いている、楽器として確立したものがあります。
ヴァイオリンは一番古い部類に入ると思います。その中ではフルートは、発明という意味では比較的最近のものでしょうね。でもまあトラヴェルソ(フルートの祖先)とかリコーダーとか、もっとバロック時代の楽器を考えれば、その楽器自身の音量とか音質の限界があったとしても、遥かにそれを超えるような、極めるような作曲がなされてきた。
それからベートーヴェンも当時の時代のピアノをさらに超えるような、ハンマークラヴィーアのその可能性を信じて作曲したという意味では非常に前衛的だったから、その演奏を現代でも自分の手で繰り返してやってみるというのはすごく大切です。
これは絵を描くことに置き換えても全く同じで、絵を描く場合、普通は必ず模写から入りますよね、デッサンとか模写から入るので、過去に書かれたものを自分で注意深く真似ると。見て真似るということはできなくて、書いてみないと真似できないですよね。そこでつい先週あたりから閃いたのが、ゴッホの絵を自分で描いてみるというのを始めまして(笑)、もちろん僕は油絵が描けないのですが、ただゴッホの場合には膨大なスケッチを残しているので、そのタッチとか見れば、それをなぞって描くことはできるんですね。そういうこともまず模倣から・・・それが第一歩かなと。
そうすると、自分では見ていたつもりなんですけれど、実際にゴッホが書簡の中で書かれたスケッチで田園風景なんて、本当に緻密に・・・自分で描いてみて初めてこれが木であり、家であり、藁の束であり、というのが全部見えて、あ、ここにお花が咲いているなんていうのも全部発見できて。この雲の描き方すごいな、みたいなね。全部当時のペンでサササっと描いてる、その力量はすごいです。彼のものの見方や、遠景と近景の書き分けとかそういうものが全て一枚に詰まっているので、それをただトレースしてなぞっただけなんですけれども、すごいです!
——学ぶという言葉は真似ぶ(まねぶ)からきていると言われていますね。
まあそういうことですね。だから本当に真似しながら得られるようになる。
——型を身につけて、できるようになるということですね。
その過程を無くして、ただスケッチブックを見て描けと言われてもそれは描けないのと同じなので、やっぱり自分でもある程度できるというのはその土台があるからかもしれない。
でもやっぱり先生に就くというのはもっと違ったものになるだろうから・・・まあまだ絵の先生には就いていないんですけれど(笑)、そういう楽しみもありますよね。
——技術が巧みになるとか、再現性が上がるという意味でも先生につくということは意味があるでしょうね。
やっぱり人間には必ず壁というのがあるので、それが本当に超えられない壁かどうかということを、その先生を信じて突破する喜びに優るものはないでしょうね。
——その先に行くためにも。
そう。それはあらゆるものが皆そうですからね。ネットで画像や動画を見て突破できるというふうに今の人は考える。それが一番手っ取り早い上に、しかもタダだと思うかもしれないけれど、でもそれは相当限られた知識や、その人にあったものでは決してない。でもそういう情報が今満ち溢れているので、その中から自分に合ったものを探す方がむしろ大変でしょう。
——そうですね、情報が沢山ありますものね。
Q10:
最後の質問です。最終的に、研究の先に先生が一番解明したいこと、究明したいことは何でらっしゃいますか?
やっぱり言葉からスタートして、音楽を研究対象としてやっていますから、芸術とか、人間が人間らしく自然に生み出すものの根っこに実は人間の言葉というものがあるんだということを科学的に証明したいですね。
そうすると鈴木先生の、最初にお話しした母語教育法というものを科学的に裏付けるということになりますし、この共同研究で夢見たことが、ホップ、ステップと、3段目のジャンプに向けて進んでいるので、一般の市民の皆さんと科学研究というものが一体となって、問題を探し、それを解決していくという一つのロールモデルみたいになるとしたら、それは本当に嬉しいことですよね。だから共同研究に皆さんの参加をお待ちしてます。
——はい、ありがとうございました!! 本日は酒井先生にお忙しい中、大変たくさんのお時間を頂戴しまして、すごく興味深いお話しを、時には結構深掘りもさせていただいて、色々伺えて本当に興味深く拝聴しました。共同研究はこれから今まさに第3段が始まったところで、またどのような結果が出てくるのかも楽しみですし、皆様の新たなご参加もお待ちしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました!
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
酒井先生に脳に関する質問をしよう!
この記事は皆様からの質問で成り立っています。たくさんの質問をお待ちいたしております!
プロフィール
酒井邦嘉(さかい くによし)
専門は言語脳科学で、人間に固有の脳機能をイメージング法などで研究している。1964年、東京都生まれ。1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。1992年東京大学医学部 助手、1995年ハーバード大学 リサーチフェロー、1996年マサチューセッツ工科大学 客員研究員、1997年東京大学大学院総合文化研究科 助教授・准教授を経て、2012年より現職。同理学系研究科物理学専攻 教授を兼任。2002年第56回毎日出版文化賞、2005年第19回塚原仲晃記念賞など受賞。著書に『言語の脳科学』(中公新書)、『脳を創る読書』(実業之日本社)、『芸術を創る脳』(東京大学出版会)、『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書)、『脳とAI』(中公選書)、『科学と芸術』(中央公論新社)、『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など。

酒井先生の研究に関する記事はこちら
(マンスリースズキより)
スズキとの共同研究を進める東京大学酒井邦嘉先生の新刊書
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/sakai2024.html

新刊『勉強しないで身につく英語』を発売
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/eigo.html
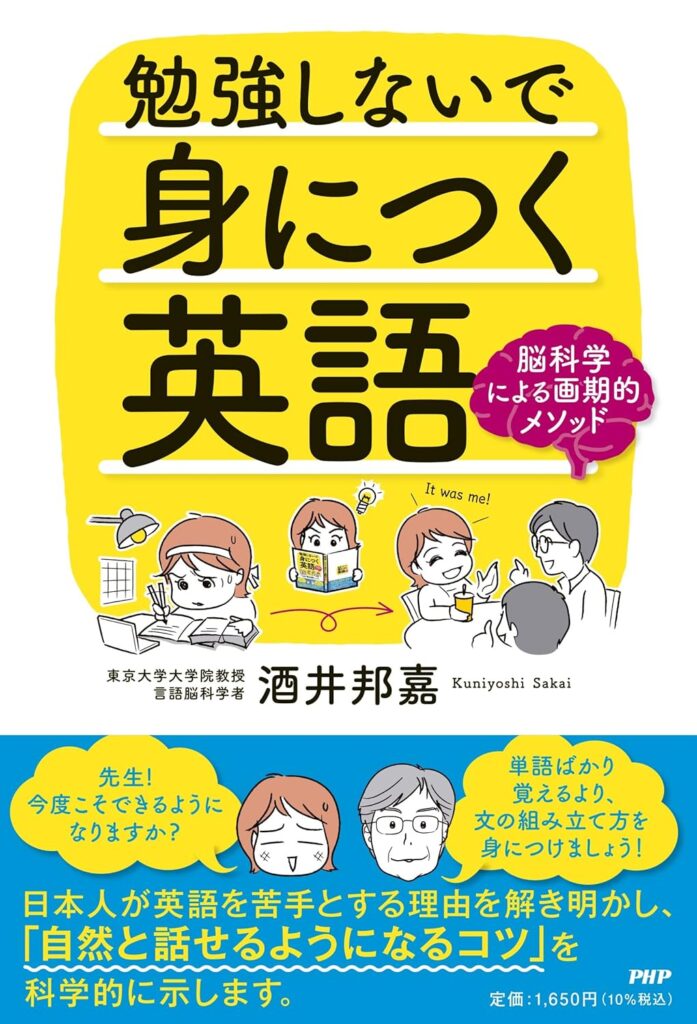
音楽の有効な習得方法を脳科学で実証
ー練習方法の違いにより左脳と右脳の活動が変化ー
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo5.html
東京大学との共同研究の論文を発表
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/collabo4.html
共同研究を話題に、毎日メディアカフェ
https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/220510-2.html
酒井邦嘉先生の東京大学教養学部報内のWeb記事
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/648/open/648-1-01.html
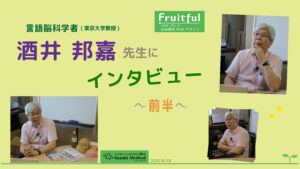

今回も個性的な質問揃いです!『脳にはさわられた感覚がありますか?』『楽器での記憶定着のコツは?』『ニューロンの出した信号が、どのようにして音楽表現につながっていくの?』『コンサートで緊張しなくなる方法は?』の4本です!

今回は「アナログvsデジタルをテーマに、どちらが人間の能力をより引き出し高めてくれるか」「睡眠は学習にどう影響するか」など4つの質問にご回答くださっています。

今回の質問は『興味のない事はどうするとすぐに覚えられますか?』と『ぼんやりと特に何もしていないときの脳活動、デフォルトモード・ネットワークの子どもの脳への影響について教えてください』です!

今回の質問は『年齢が増えるとニューロンも増えるのでしょうか?』『ニューロンの数は決まっているのですか?それとも人によって違うのですか?』『ニューロンを増やすのに有効なことはありますか?また、ニューロンの働きに悪い影響を及ぼすものはありますか?』です。興味深い質問ばかりです!

酒井先生が脳に関する皆さんの疑問にお答えくださるシリーズ。今回の質問は『頭の良い・悪いって、脳科学的にはどういう状態のことを言いますか? 例えば、計算の得意な人と苦手な人の脳の違い、音楽や楽器演奏の得意な人とそうでない人の脳の違いはどんなところにあるのでしょうか?』

読者の皆さんからの質問に酒井先生がお答えくださるシリーズ。今回は①ニューロンはどのようにスケッチしたのか? ②ニューロンひとつひとつの働きは? の2つの質問への回答です!

脳が持つ最大の特徴、それは使い方、育て方によって機能がカスタマイズされ続けること!この驚くべき能力「可塑性」について、スズキ・メソードと共同研究をしている脳科学者、酒井邦嘉先生が解説してくださいます。