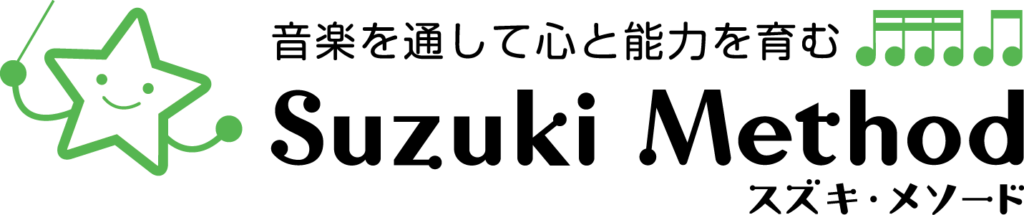
第8回 不調を防ぐ工夫:睡眠時間について考える
東京大学教授
精神科医師・医学博士
佐々木 司
前回は、思春期がメンタルの不調の起こりやすい時期であること、また精神疾患の多くは思春期から増え始め、10代の中頃から終わりにかけて発症のピークを迎える病気が少なくないことをお話しました。今回からはそのような不調を防ぐための工夫、特に毎日の生活の中で気をつけられる工夫についてお話したいと思います。具体的には睡眠や運動の習慣、気分転換、居場所と仲間作りなどについてお話します。また音楽と楽器演奏の役割についても、私自身の経験を含めてもお話できればと思います。なお字数の関係で今回は、睡眠習慣の中でもその量、つまり「睡眠時間」に焦点をあててお話したいと思います。
まずは十分な睡眠時間が大事
睡眠はメンタルの健康を保つうえで最も大事なことの一つです。特に日本人を含めて東アジアの人は、ヨーロッパやアメリカの人たちと比べて、子どもでも明らかに睡眠時間が短いので、一層の注意が必要です(後ろの図2で詳しく説明します)。
図1を見てください。これは日本の中学生・高校生約1万8千人を対象としたアンケート調査を私と共同研究者がチームで解析した結果です。普段の睡眠時間と、うつや不安が一定以上のレベルに達するリスクとの関係(統計学の言葉で言うとオッズ比)を示しています。上段は中学生、下段は高校生で、いずれも左側は男子、右側は女子です。
佐々木司(ささき つかさ)
東京大学名誉教授、公立学校共済組合関東中央病院メンタルヘルスセンター長、精神科医師・医学博士。小学校入学後よりスズキ・メソードでヴァイオリンを習う。東京大学医学部医学科卒後、同附属病院精神科で研修。クラーク精神医学研究所(カナダ、トロント市)に留学。東京大学保健センター副センター長、同精神保健支援室長(教授)、同教育学研究科健康教育学分野教授などを歴任。思春期の精神保健、精神疾患の疫学研究、学校の精神保健リテラシー向上などに取り組んでいる。日本不安症学会副理事長、日本学校保健学会常任理事、日本精神衛生会理事を兼務。
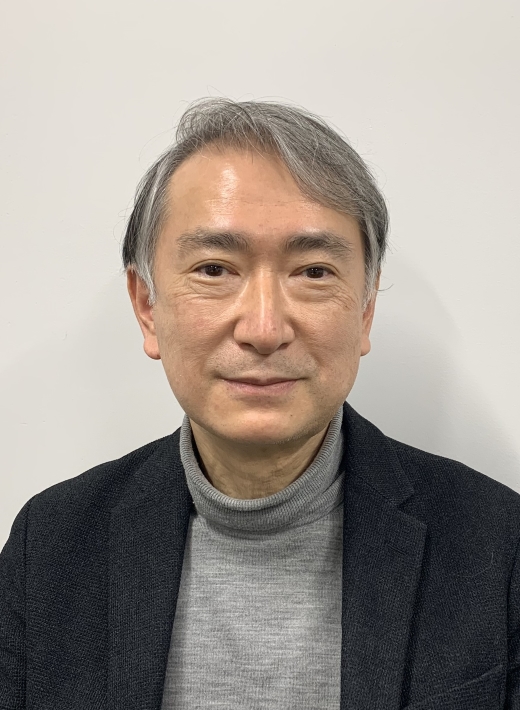

「うつ」や「摂食障害」など、生活や学業への影響が顕著に出るメンタルヘルスの問題について、専門家である佐々木先生がお話しくださいます。メンタルの病気の実態や、どのような時に疑われるのかを解説してくださいます。

親として子どもと日々対峙する中、つい「失敗」してしまうことも・・・「親のこころ子知らず」なのか「子のこころ親知らず」なのか、少し遠めから眺め考えさせてくれる回です。

思春期の子どもたちと親との関係を考えるうえで避けられない大きなテーマ「反抗期」。親の注意に対する幼児期との受け取り方の違いや距離感の保ち方、いつまで続きどこまで許容するかなど、親世代が直面する課題を分かりやすく解説します。

親子関係もセンシティブなこの時期に、保護者は子どもたちにどのように注意を伝えるべきか、考えます。

今回は、思春期のこころの移り変わりを把握していくのに前提となる脳のメカニズムを鳥瞰します。今後の回の理解に繋がる必須の知識です。

子どもから大人へ成長していく過程で必ず通る「思春期」。その大切で輝かしい時期の、心のあり様を考える新シリーズです。




