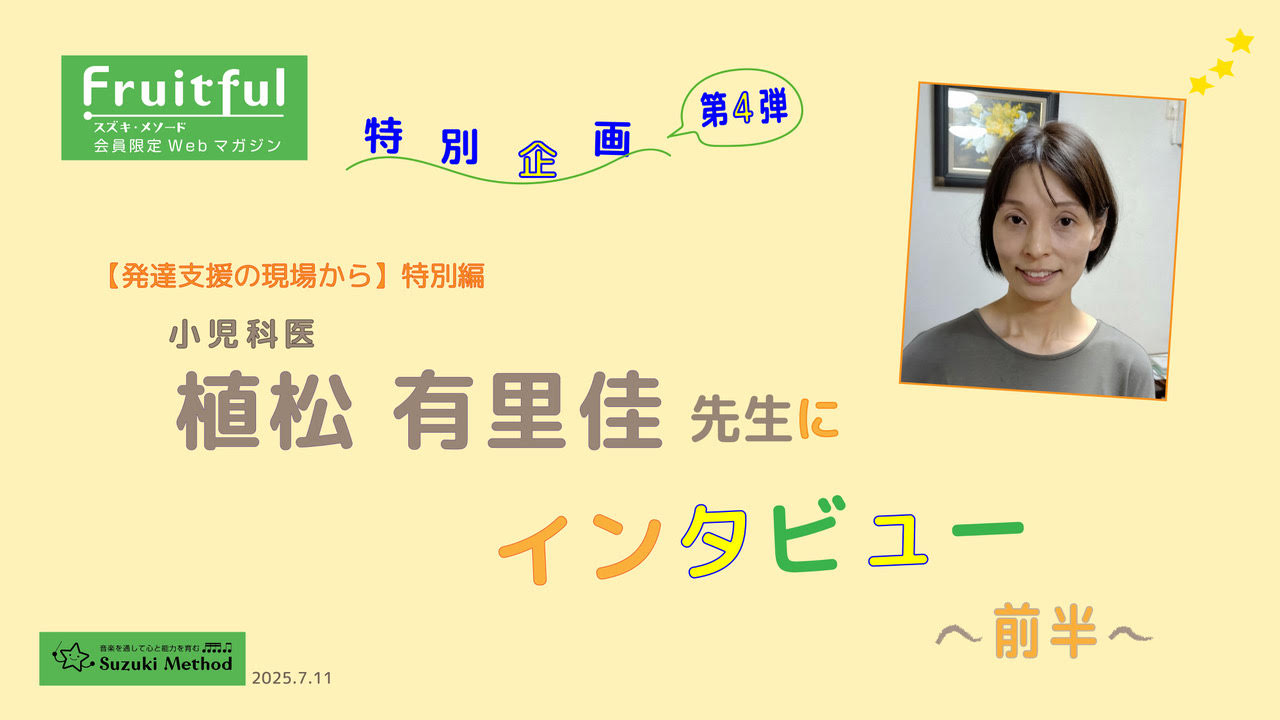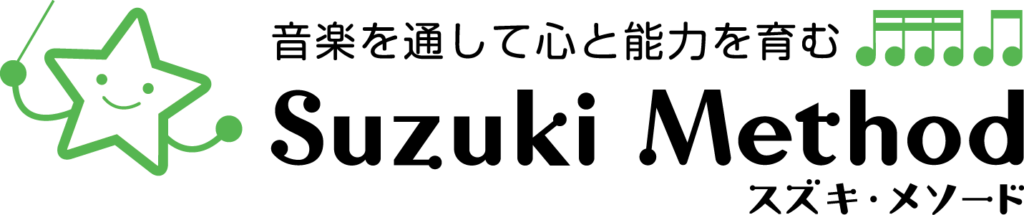
今回の「発達支援の現場から」は特別編として、2024年の夏期学校の際に収録した植松有里佳先生のインタビューを、動画とテキストでお届けいたします。全2回でお送りいたしますので、後半もどうぞお楽しみに!
Questions
- 体の発達の観点から見ると、3歳4歳で楽器を弾くのは早すぎるような感じがしますが、いかがでしょうか?
- 耳だけで聞く能力と、見ながら聞く能力は、発達上で、耳だけで聞く方に利点が多いのでしょうか?
- 昼寝の時、自然に起きるのを待ったほうが良いのかな、とわざと起こしていません。夜の入眠の方を優先させるために、昼寝、もしくは朝も起こした方が良いのでしょうか?
- 食事時、テレビを見ながら内容について会話するのはNG?
- 身体を使った遊びの具体例と、状況に応じた対応例を教えてください。
- 子どもたちが映像メディアに接する時間をできるだけ少なくしたいと思っています。ただ、教育的なこと、 良い知識を増やす内容のものでも見過ぎない方が良いのでしょうか?
プロフィール
植松有里佳
7歳の女の子の母。小児科医。専門は小児神経学で、神経難病からてんかん、発達障害まで幅広く診療している。

あわせて読みたい


発達支援の現場から 13
第13回「子どもが社会のルールを学ぶ時」
昨今、子どもが我慢できなくなったり周囲に合わせることが難しかったり・・・そんな現象の原因はどこにあるのでしょうか。発達支援の現場から感じることをお書きくださいました。
昨今、子どもが我慢できなくなったり周囲に合わせることが難しかったり・・・そんな現象の原因はどこにあるのでしょうか。発達支援の現場から感じることをお書きくださいました。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 12
第12回
「子どもの映像メディアとの付き合い方」
今回は、実際の診療でのケースを例に、メディアとの接触時間が子どもの生活に与えてしまう影響の大きさを考えます。
今回は、実際の診療でのケースを例に、メディアとの接触時間が子どもの生活に与えてしまう影響の大きさを考えます。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 11
第11回
「子どもと映像メディア」~学齢編~
前回に引き続き、現代の生活の中に深く入り込んでいる映像メディアに潜んだ諸問題を、目に見えるようにして解説していきます。今回は学齢期以降の子どもにフォーカスを当てます。
前回に引き続き、現代の生活の中に深く入り込んでいる映像メディアに潜んだ諸問題を、目に見えるようにして解説していきます。今回は学齢期以降の子どもにフォーカスを当てます。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 10
第10回
「子どもと映像メディア」~幼少期編~
現代の子育てで最も気になるトピックスの一つであるメディアとの関わり方について、小児科医の目線からの提言です。
現代の子育てで最も気になるトピックスの一つであるメディアとの関わり方について、小児科医の目線からの提言です。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 8
第8回「自立」と「自律」
第4回の記事に寄せられた質問への回答から、思春期に向かう子どもたちにとって、あるいは親自身が何を指針とするべきかのヒントが示されています。
第4回の記事に寄せられた質問への回答から、思春期に向かう子どもたちにとって、あるいは親自身が何を指針とするべきかのヒントが示されています。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 7
第7回「子どもの発達と身体を使った遊び」
子どもたちが遊びを通して身につけていくものは何なのか? 家でも外でも、家族や仲間と自然に育むことのできる能力についてお話しします。
子どもたちが遊びを通して身につけていくものは何なのか? 家でも外でも、家族や仲間と自然に育むことのできる能力についてお話しします。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 5
第5回「子どもの睡眠」
夏休みの時期につい乱れがちになる睡眠。年齢に応じて必要な睡眠時間や、学習との関連、さらにお昼寝をした場合の就寝時間への影響をお話しします。
夏休みの時期につい乱れがちになる睡眠。年齢に応じて必要な睡眠時間や、学習との関連、さらにお昼寝をした場合の就寝時間への影響をお話しします。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 4
第4回「子どもの発達、思春期」
今回は思春期の子どもの身体の発達と、それに伴う心理の変化(=二次反抗期)に対し、どう対応していくのが良いのか・・・小児科医の立場からの提言です。寄せられた質問への回答もございます。
今回は思春期の子どもの身体の発達と、それに伴う心理の変化(=二次反抗期)に対し、どう対応していくのが良いのか・・・小児科医の立場からの提言です。寄せられた質問への回答もございます。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 3
第3回「子どもの言葉の発達」
子どもは運動機能の発達が進むと、言葉の発達も促されます。さらに年齢とともに自我が目覚め、一次反抗期へ・・・そのとき、周囲の大人の心構えはどうすれば良いのでしょうか?
子どもは運動機能の発達が進むと、言葉の発達も促されます。さらに年齢とともに自我が目覚め、一次反抗期へ・・・そのとき、周囲の大人の心構えはどうすれば良いのでしょうか?
あわせて読みたい


発達支援の現場から 2
第2回「子どもの運動発達」
生まれてから4‐5歳まで、子どもはどのような段階を経て運動能力を発達させていくのでしょうか?全身運動から手先を使う作業に至るまでの道筋を解説します。
生まれてから4‐5歳まで、子どもはどのような段階を経て運動能力を発達させていくのでしょうか?全身運動から手先を使う作業に至るまでの道筋を解説します。
あわせて読みたい


発達支援の現場から 1
第1回「子どもの発達と愛着形成」
子ども時代に大切なことを小児科医の視点からお届けするシリーズ。今回は親子関係の基盤や子どもの成長の土台となる「愛着形成」についてです。「愛着」って何?どうやって育むの?うまくいかないとどうなるの?など、様々な疑問を解説します。
子ども時代に大切なことを小児科医の視点からお届けするシリーズ。今回は親子関係の基盤や子どもの成長の土台となる「愛着形成」についてです。「愛着」って何?どうやって育むの?うまくいかないとどうなるの?など、様々な疑問を解説します。