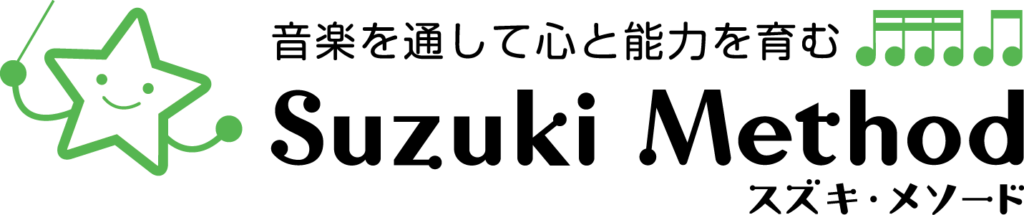
第5回 「反抗期」について考える
東京大学教授
精神科医師・医学博士
佐々木 司
前回は子どもを叱ったり注意したりするときに気を付けるべき点について書きました。子どもの気持ちに残るような注意の仕方や冷静に注意するにはどうしたら良いかなどです。
ただ、一生懸命気を使いながら注意しても、子どもの方で聞いてくれないこともあります。特に思春期の子どもは不機嫌になりやすく、親の言うことを聞いてくれないこと、反抗的で手に負えないことも日常茶飯事です。
今回は思春期のこの問題、反抗期の問題について考えてみたいと思います。
プロフィール
佐々木司(ささき つかさ)
東京大学名誉教授、公立学校共済組合関東中央病院メンタルヘルスセンター長、精神科医師・医学博士。小学校入学後よりスズキ・メソードでヴァイオリンを習う。東京大学医学部医学科卒後、同附属病院精神科で研修。クラーク精神医学研究所(カナダ、トロント市)に留学。東京大学保健センター副センター長、同精神保健支援室長(教授)、同教育学研究科健康教育学分野教授などを歴任。思春期の精神保健、精神疾患の疫学研究、学校の精神保健リテラシー向上などに取り組んでいる。日本不安症学会副理事長、日本学校保健学会常任理事、日本精神衛生会理事を兼務。
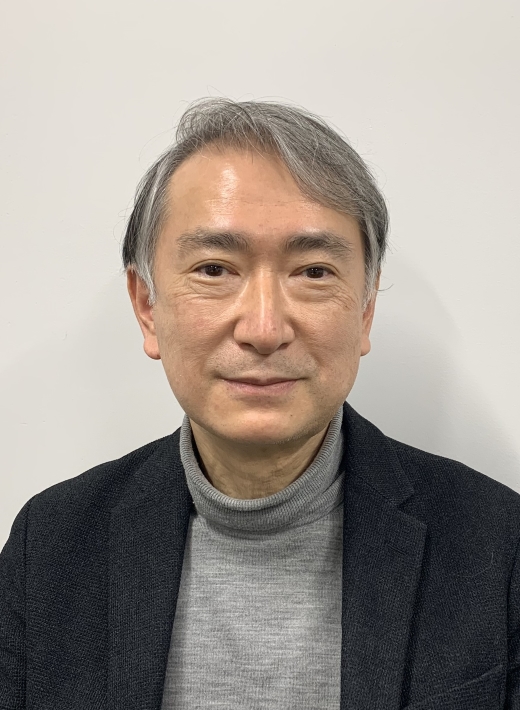
あわせて読みたい


親子で考える「思春期のこころ」6
第6回「子どものことで自分を責めてしまう時に」
親として子どもと日々対峙する中、つい「失敗」してしまうことも・・・「親のこころ子知らず」なのか「子のこころ親知らず」なのか、少し遠めから眺め考えさせてくれる回です。
親として子どもと日々対峙する中、つい「失敗」してしまうことも・・・「親のこころ子知らず」なのか「子のこころ親知らず」なのか、少し遠めから眺め考えさせてくれる回です。
あわせて読みたい


親子で考える「思春期のこころ」4
第4回「思春期の親子関係 - その2:子供に注意する時の注意」
親子関係もセンシティブなこの時期に、保護者は子どもたちにどのように注意を伝えるべきか、考えます。
親子関係もセンシティブなこの時期に、保護者は子どもたちにどのように注意を伝えるべきか、考えます。
あわせて読みたい


親子で考える「思春期のこころ」2
第2回「脳の成長・発達と思春期」
今回は、思春期のこころの移り変わりを把握していくのに前提となる脳のメカニズムを鳥瞰します。今後の回の理解に繋がる必須の知識です。
今回は、思春期のこころの移り変わりを把握していくのに前提となる脳のメカニズムを鳥瞰します。今後の回の理解に繋がる必須の知識です。
あわせて読みたい


親子で考える「思春期のこころ」1
第1回「思春期」ってなんだろう - その1
子どもから大人へ成長していく過程で必ず通る「思春期」。その大切で輝かしい時期の、心のあり様を考える新シリーズです。
子どもから大人へ成長していく過程で必ず通る「思春期」。その大切で輝かしい時期の、心のあり様を考える新シリーズです。




